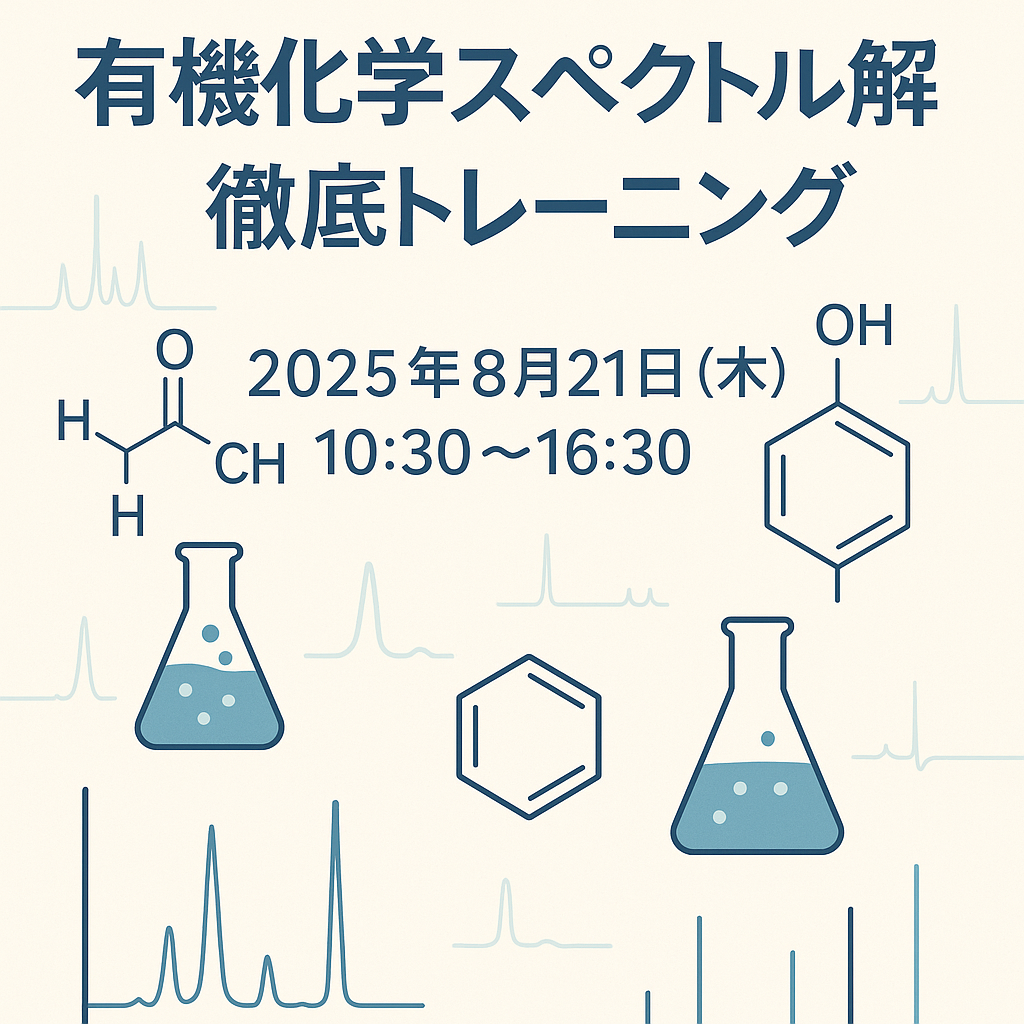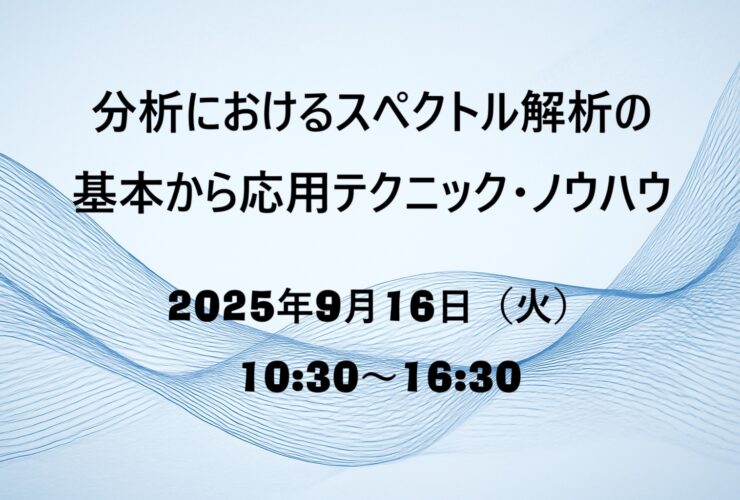演習問題で身につける 有機化学スペクトル解析 徹底トレーニング
演習問題で身につける
有機化学スペクトル解析 徹底トレーニング
スペクトル解析がわかる!読める!実務で使える!
基礎・コツ・問題が満載の集中講義
セミナー概要
🎯 こんな方におすすめです
- IR、MS、NMRのスペクトル解析をもっとはやく、上手になりたい!
- 実務に使えるスペクトルの読み方とコツをちゃんと学んでみたい!
- 未知の化合物や初めて見るスペクトルでも生成物の構造を悩まずに予想したい!
🔬 受講形態
🎥 Live配信(アーカイブ配信付)
開催日当日に受講できる、その場で質問できる、翌日以降に動画で復習(7日間)
📱 アーカイブ配信
開催日当日の予定が見えない、動画を見ながらじっくり学びたい(14日間)
💰 受講料
55,000円(税込)
E-Mail案内登録価格:52,250円(税込)
🎁 特別割引:E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料!
📚 研修パック:3名以上の申込みで1人あたり19,800円
👨🏫 講師プロフィール
矢野 将文 氏
関西大学 化学生命工学部 准教授
専門:有機合成化学・構造有機化学
🎓 経歴
• 平成10年 博士(理学)取得(大阪市立大学)
• 平成11年 日本学術振興会特別研究員(PD)
• 平成12年 関西大学 工学部 教養化学教室 助手
• 平成17年 関西大学 工学部 教養化学教室 専任講師
• 平成22年 関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 准教授
🏆 受賞歴・著書
• エスペック環境研究奨励賞(2024年8月)
• 著書:「有機化学 1000本ノック 【スペクトル解析編】」(化学同人 2022)
• 著書:「トコトンやさしい有機化学」(化学同人 2025)
✨ 「有機化学1000本ノック」シリーズの著者が登板!
圧倒的な収録問題数(1000題)が特長の人気シリーズの著者による、実践的なスペクトル解析セミナーです。
📋 プログラム詳細
1. 水素不足指標(IHD)を計算しよう
- 分子式からIHDを計算する方法
- 構造式からIHDを求める手法
2. 赤外吸収スペクトル、ここを見よう
- そもそもIRスペクトル、何を見てるの?
- カルボニルある?ない?
- ヒドロキシ基、アミノ基どこに出る?
3. 質量スペクトルから何がわかる?
- そもそも質量スペクトル、何を見てるの?
- 分子量はどこでわかる?
- 特徴あるピークを見つけて、含まれている官能基を推定しよう
4. 13C-NMRから何がわかる?
- その化合物、何個の炭素が含まれている?何種類の炭素が含まれている?
- スペクトルから何種類の炭素があるかを読み取ろう
- 各炭素に結合している水素の数を決めよう(DEPT、オフレゾナンス、プロトンデカップル)
- 各炭素はどんな環境にあるか決めよう。混成軌道は?隣の元素は何?(マスターチャートの読み取り)
5. 1H-NMRから何がわかる?
- その化合物、何個の水素が含まれている?何種類の水素が含まれている?
- スペクトルから何種類の水素があるかを読み取ろう
- どの炭素とどの炭素が隣同士かな?(ビシナルカップリング:n+1則)
- こんな場合もカップリングする(ジェミナルカップリング、ロングレンジカップリング)
- 各炭素はどんな環境にあるか決めよう。混成軌道は?隣の元素は何?(マスターチャートの読み取り)
6. さあ、構造解析してみよう
- まずIHDを計算して、大まかなイメージをつかもう
- 過不足がないように含まれている部品(置換基)をリストアップしよう
- 部品をつないでいこう。端にくる置換基はどれ?真ん中に来る置換基はどれ?
- 異性体の候補を比較して、構造決定しよう
□ 質疑応答
講師への直接質問でさらに理解を深めましょう
🎯 セミナー趣旨
スペクトル解析の講義は大学二年生頃に必修になっている大学が多いと思います。グニャグニャした曲線が書かれた図を渡されて、「ここから目的物の構造式を決めてください」と課題が出たりします。最初は全くわからないと思います。
スペクトル解析が大変なのは、今までに高校、大学で学習してきたいずれの科目の延長でもないということです。「よくわからないけど、この化合物が正解なのか。このスペクトルの形、覚えてしまおう」と思っても、スペクトルが読めるようにはなりません。化合物の種類が違えば、得られるスペクトルは異なってきます。間違いなく丸覚えは不可能です。
💡 実は、サクサクとスペクトルを解析できる人の秘密
スペクトルの全てのピークを読んでいません。複数の測定方法から得られたスペクトルから必要な情報だけを読み出し、正解となる構造式に最短ルートで論理的にアプローチしています。
この講座では、各測定法からどのような情報が得られるかを理解し、スペクトルの読み方を順番に説明します。これらの作業を通じて、どんな構造が含まれているかがわかってきます。これらの基本的ルールを身に着けておけば、初めて見るスペクトルでも、生成物の構造が予想できるようになってきます。
そして、さらに理解を深められるよう、十分な量の演習を準備しています。簡単な分子式、構造式、スペクトルの問題から始まりますが、徐々に複雑になっていきます。複数の情報を組み合わせないと解けない問題も出てきます。「この分光法では分子の何を測っているのか」、さらに「スペクトルのどこを見れば、どんな情報が得られるか」をつねに意識して、構造決定に必要な情報をスペクトルから読み出せるようになりましょう。
📞 お問い合わせ
株式会社イーコンプライアンス 丁田
〒630-0244 奈良県生駒市東松ヶ丘1-2 奥田第一ビル102