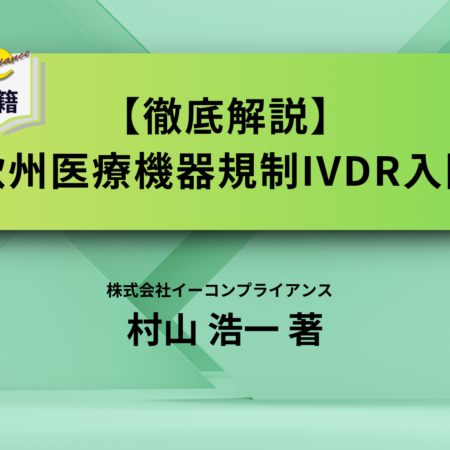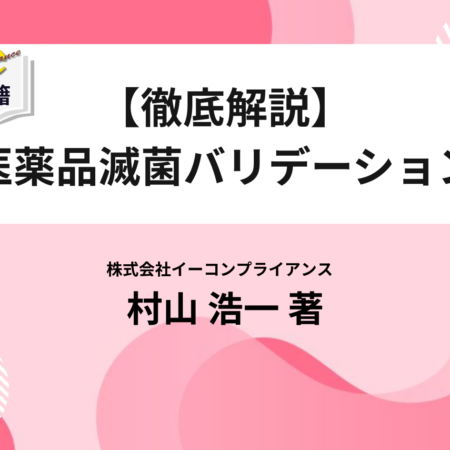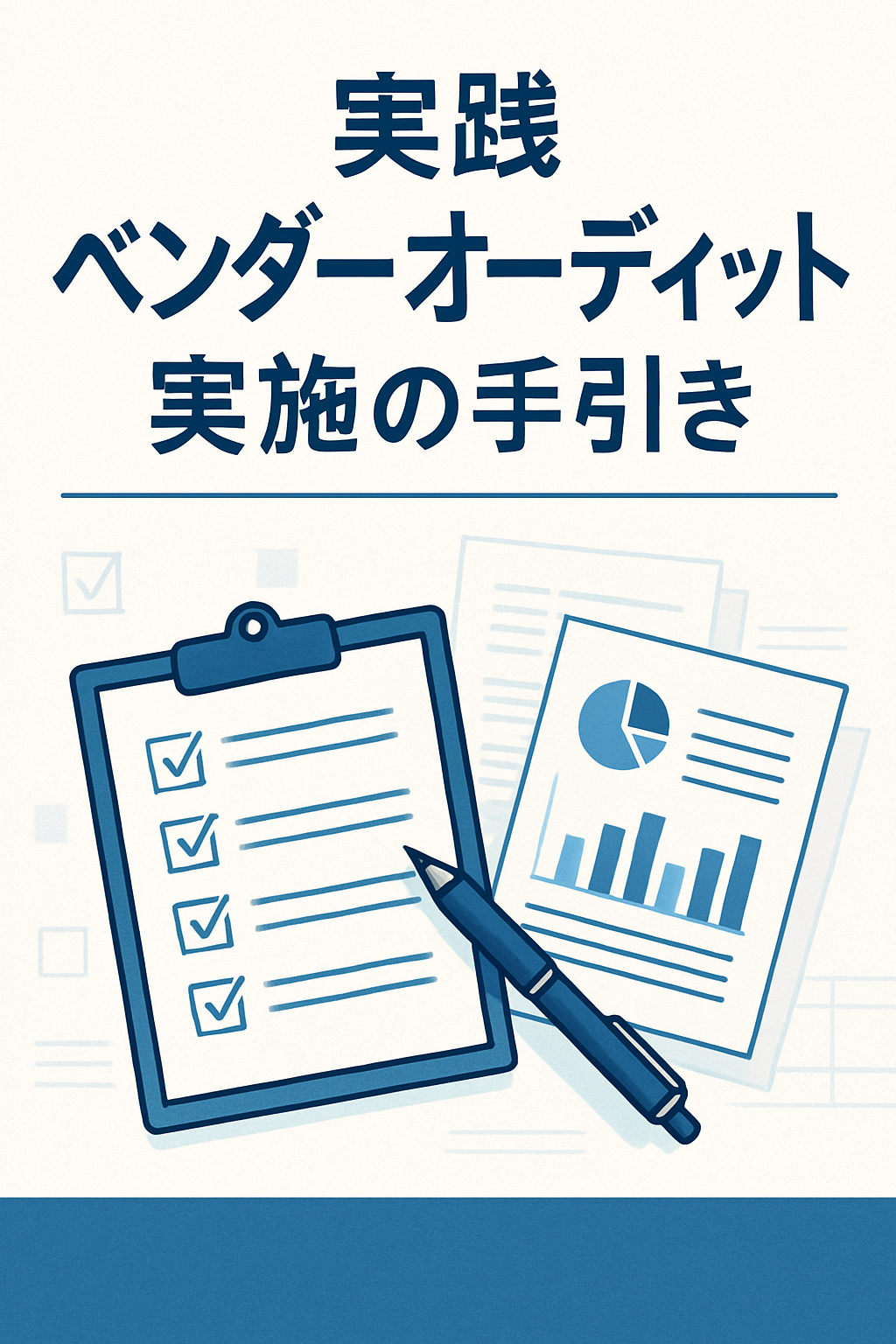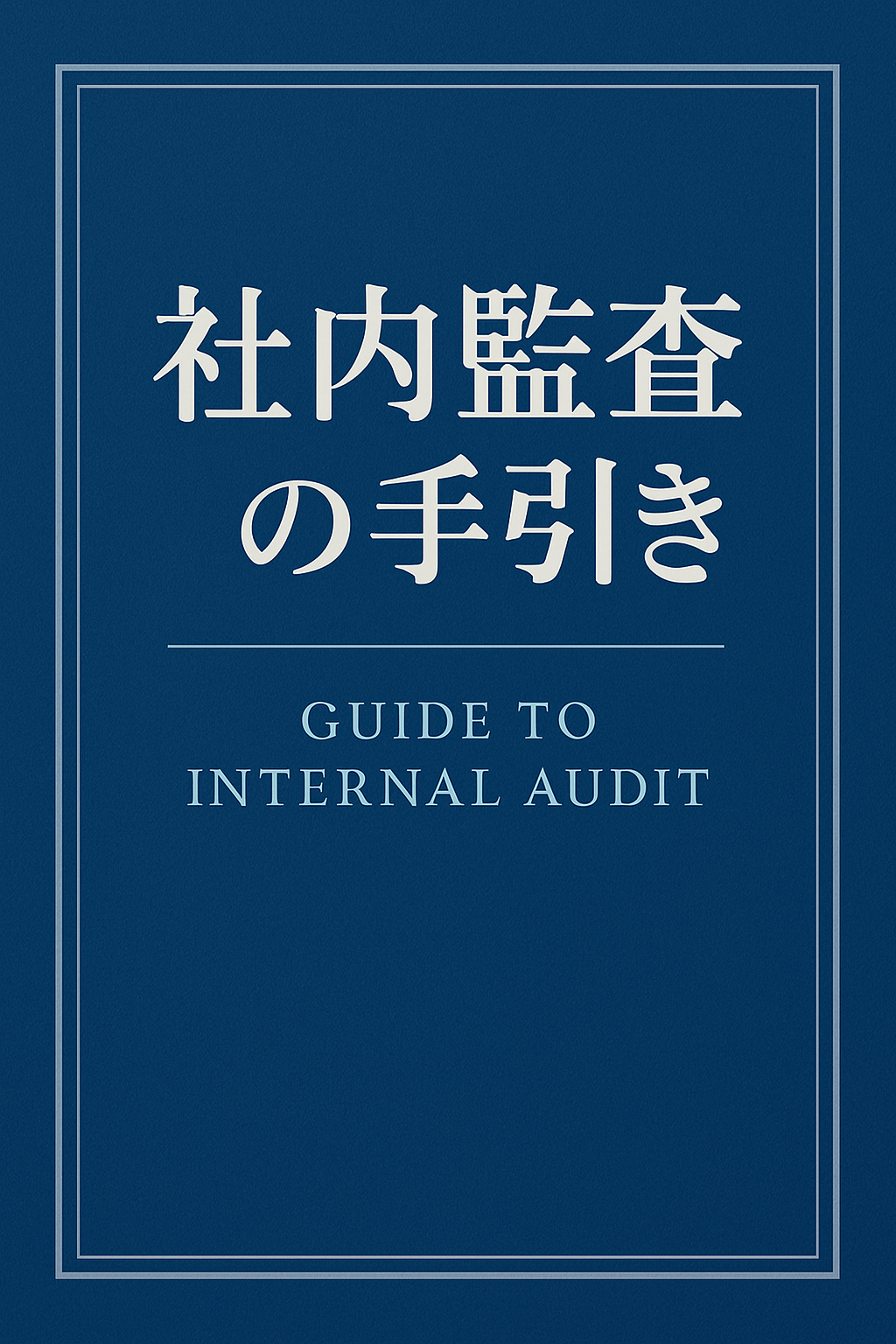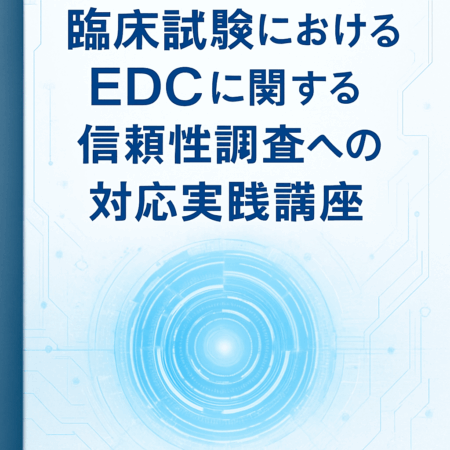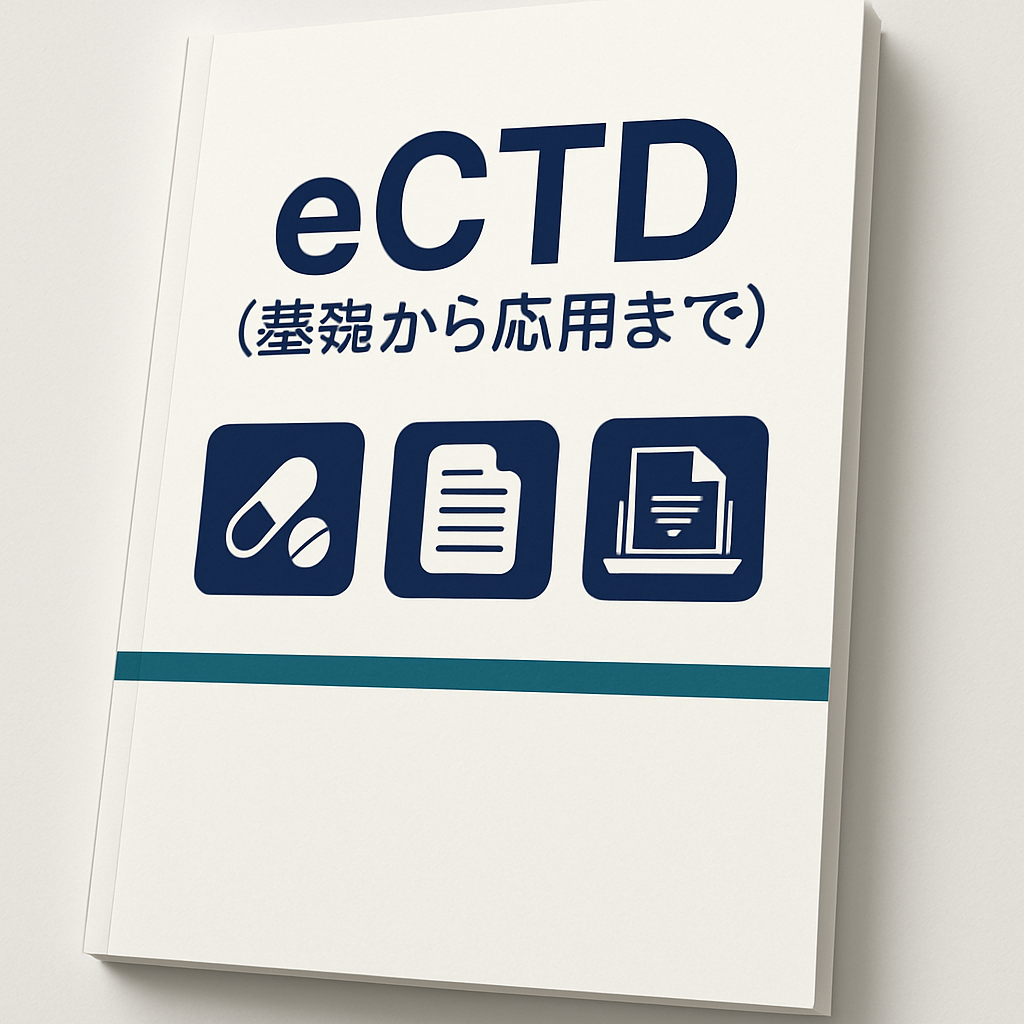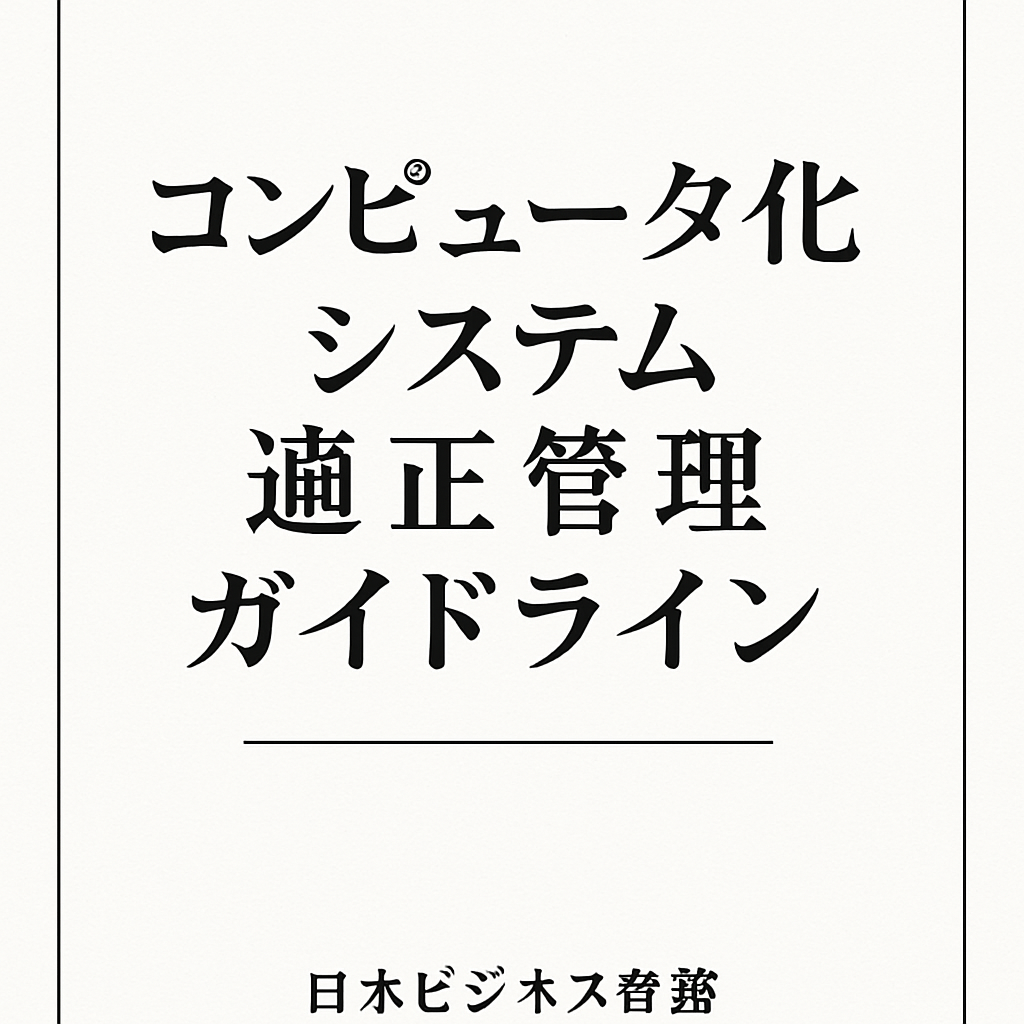書籍
専門書籍一覧
[書籍] <ebook><テクニカルトレンドレポート> シリーズ1 [FOWLP・FOPLP/混載部品化] 次世代半導体パッケージの開発動向と 今後必要なパッケージング・材料技術
<テクニカルトレンドレポート>シリーズ1 [FOWLP・FOPLP/混載部品化]
次世代半導体パッケージの開発動向と今後必要なパッケージング・材料技術
現在のパッケージング技術確立までの開発経緯から先端PKGが抱える課題の解決のための封止技術・材料の開発指針まで早掴み!
| 配信開始日 | 2017年7月28日 |
|---|---|
| フォーマット | PDF(コンテンツ保護のためアプリケーション「bookend」より閲覧) ※このebookは印刷不可・コピー不可です。 |
| 体裁 | B5 114頁 |
| 価格(税込) | 22,000円(本体20,000円+税2,000円) |
| アカウント数 | 5アカウント ※購入者以外に最大4アカウントまで追加可能(無料) 閲覧可能PC数 :2台/1アカウント(同一アカウントに限る) |
| カテゴリ | 半導体, パッケージング, FOWLP, FOPLP, 材料技術 |
先端パッケージ市場を攻略するために
日本企業はその強みをどう活かし、取り組んでいくべきか
現在の先端半導体パッケージング技術の発展経緯と今後の方向性について述べます。2005年に開発されたFOWLP(Fan-Out Wafer Level Package)は革新的でありながら当初普及しなかった理由、前工程PKGと後工程PKGの技術的攻防による進化、そして主要半導体メーカーの最新戦略について考察します。
注目のトレンドを徹底解説
-
iphoneへの採用で脚光を浴びる<FOWLP> -
FOWLPと同様の設計思想で後工程PKGとして応用が検討されている<FOPLP> -
自動運転やIoTの潮流でニーズが増す<混載部品化PKG>
これらの新しいパッケージで必要になる新しい封止技術・材料「薄層封止技術・材料」「混載封止・4D実装ー3D材料」とはどのようなものか?半導体パッケージ技術に精通する著者が解説します。
現在の先端パッケージング技術が構築されるまでの経緯
半導体開発の動向、高集積・高密度化、低コスト化、製造プロセスの最適化、封止材料組成の検討…これからのパッケージング技術を考える上で欠かせない、これまでの技術開発経緯を解説!
FOWLPの誕生と進化
2005年開発当時のFOWLPはどのような経緯で誕生し、何故花開かなかったのか?前工程PKG vs 後工程PKGの攻防で半導体開発はそれぞれどのような進化を遂げたのか?
最新の戦略と今後の方向性
最近の主要半導体メーカはどのような戦略・方向性に舵を切っているのか?これらの開発経緯・近年の動向を紐解きながら、今後の封止技術への要求、材料の必要特性に迫ります。
FO型パッケージの最新動向と課題
現在のFO型パッケージが抱える課題
現在FO型パッケージ<FOWLP/FOPLP>に適用されている封止方法はどのようなものか?チップ裏面封止に使用されている封止材料、再配線加工に使用されている絶縁材料…これらの材料はどのような特性面で課題を抱えているのか?液状材料・粉体材料・シート材料・・・どれが良いのか?
薄層封止技術の重要性
FO型パッケージの成長のカギを握る、外部接続回路の薄層封止技術とはどのようなものか?再配線法の課題を解決するための封止技術とは?子基板法の課題を解決するための封止技術とは?
必要な薄層材料とは
薄層封止技術を実現するために必要な薄層材料とは?信頼性に優れる薄型外部接続回路の加工に必要な絶縁材料の特性とは?既存材料ではどのような特性が不足しているのか?必要特性を満たすための具体的な材料技術とはなにか?
FO型パッケージでは、チップ裏面封止材料や再配線加工用絶縁材料に特性面での課題があります。液状、粉体、シートなど様々な材料形態がありますが、FO型パッケージの成長には外部接続回路の薄層封止技術が重要です。
混載部品化パッケージの革新
混載部品化パッケージの傾向が強まり、従来の電気・電子部品がパッケージの一部として統合されるようになっています。これにより従来の塗布法・浸入法による接着保護から新たな封止手法への移行が必要となり、「4D実装」と「3D材料」という要素技術が重要になっています。
混載部品化における主要課題
-
これまで電気・電子部品として扱われてきた部品がなぜPKGの一部として扱われるようになるのか? -
混載部品の封止は、従来行われてきた、塗布法・浸入法による接着保護の手法からどう変わるのか? -
これら既存の封止技術(封止方法・材料)が抱える問題点、達成できない要求特性とは?
さらに、混載部品化の流れに対応する混載封止の要素技術―4D実装と3D材料とは?混載部品化により新たに必要となる評価試験項目とは?従来の試験方法から改良すべき点、新たに取り入れる必要がある試験方法とは?などなど、本書のChapter3・4を中心に解説します。
著者紹介
目次
本書の構成
関連商品
お問い合わせ