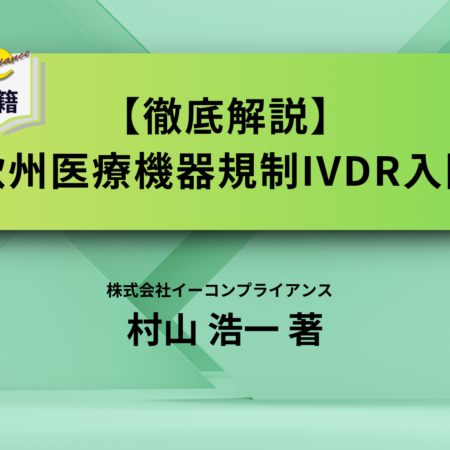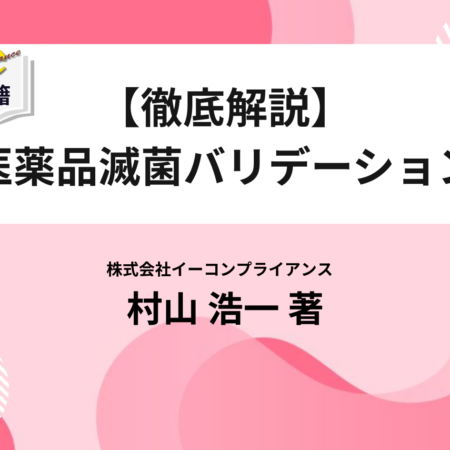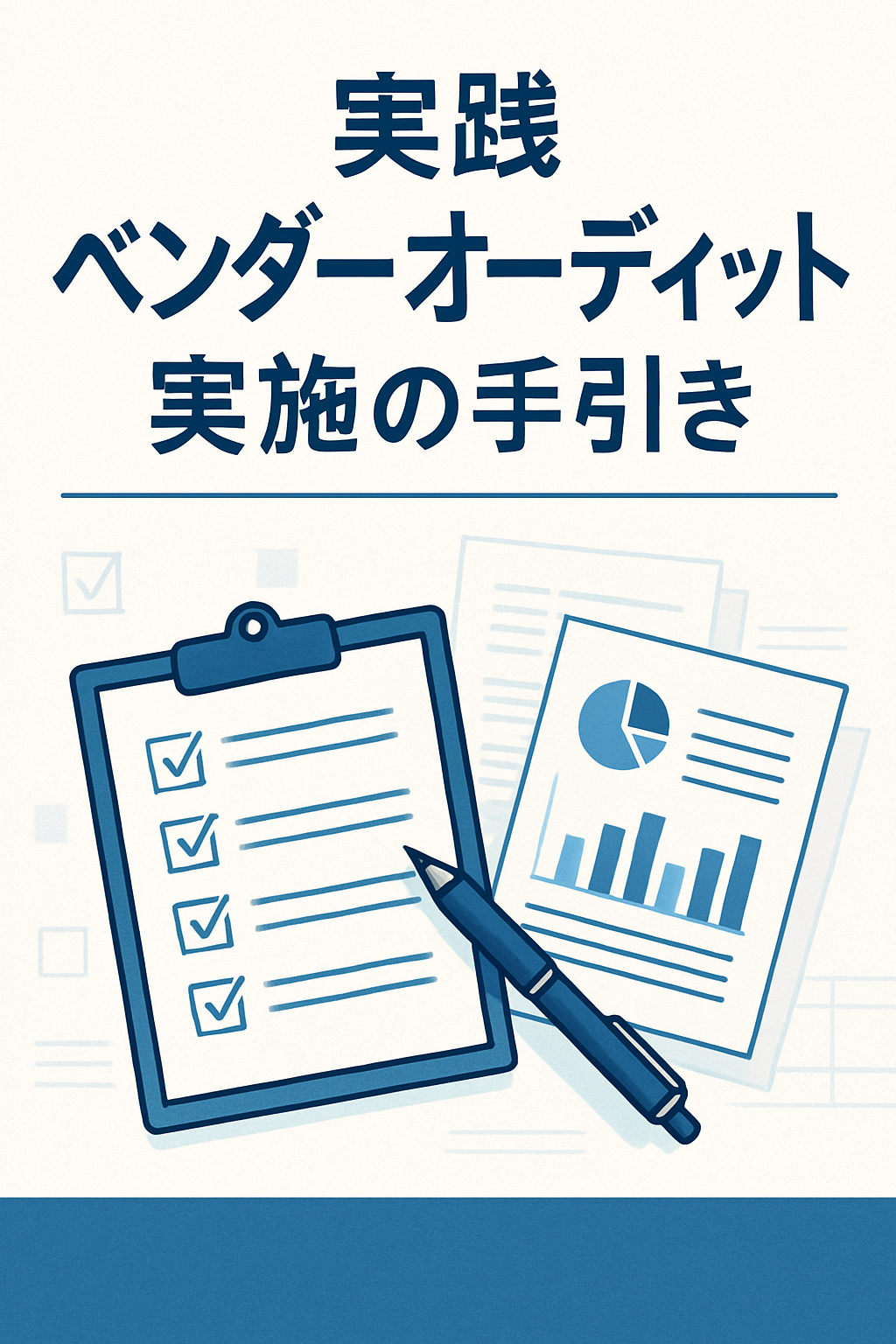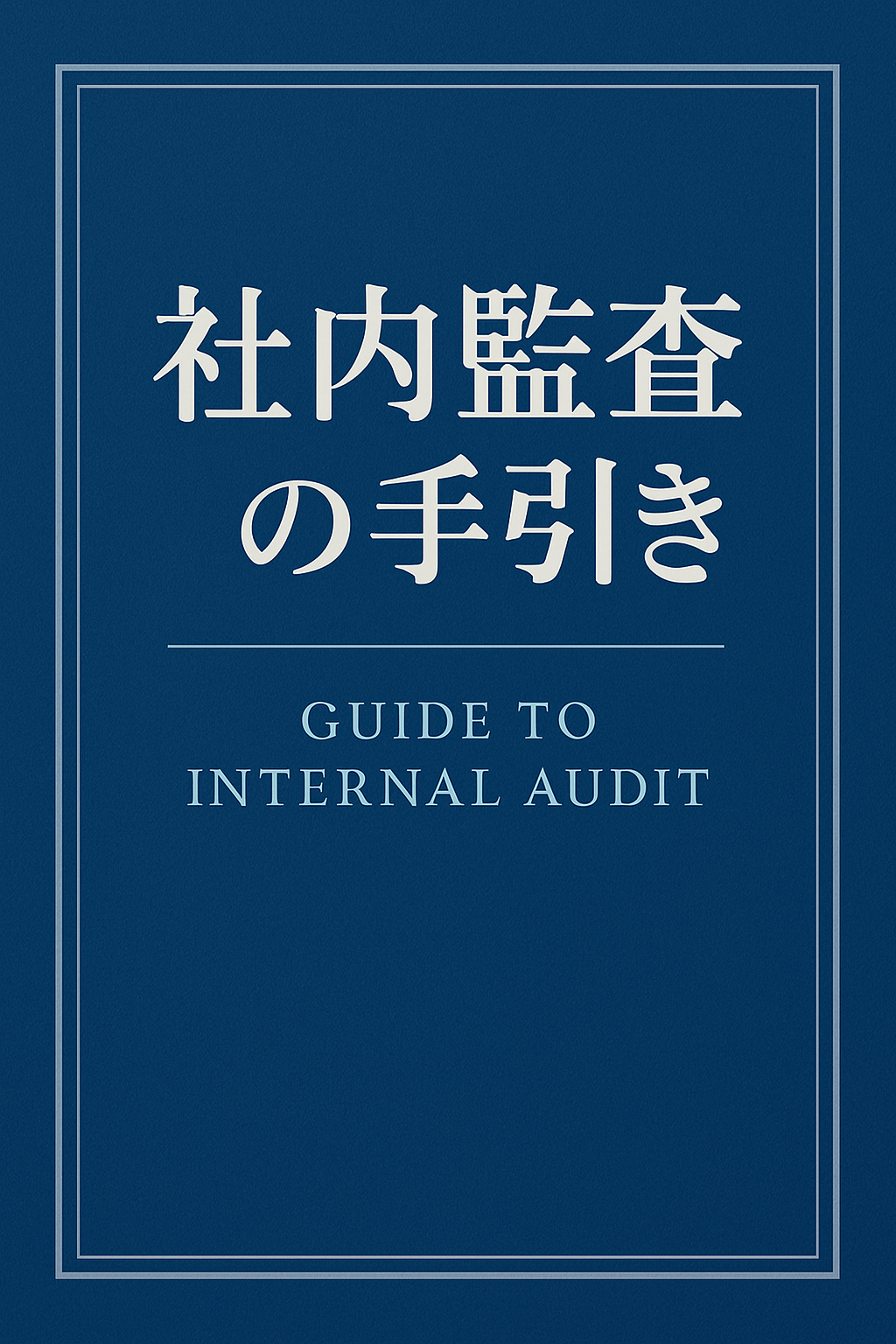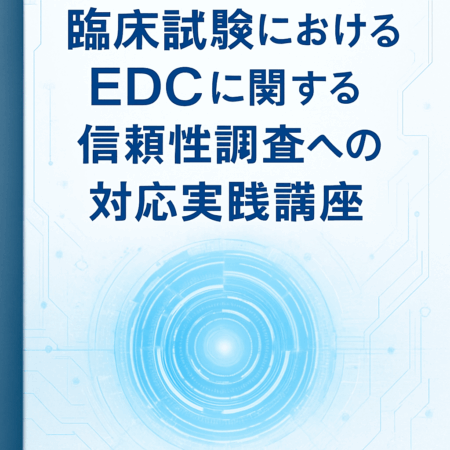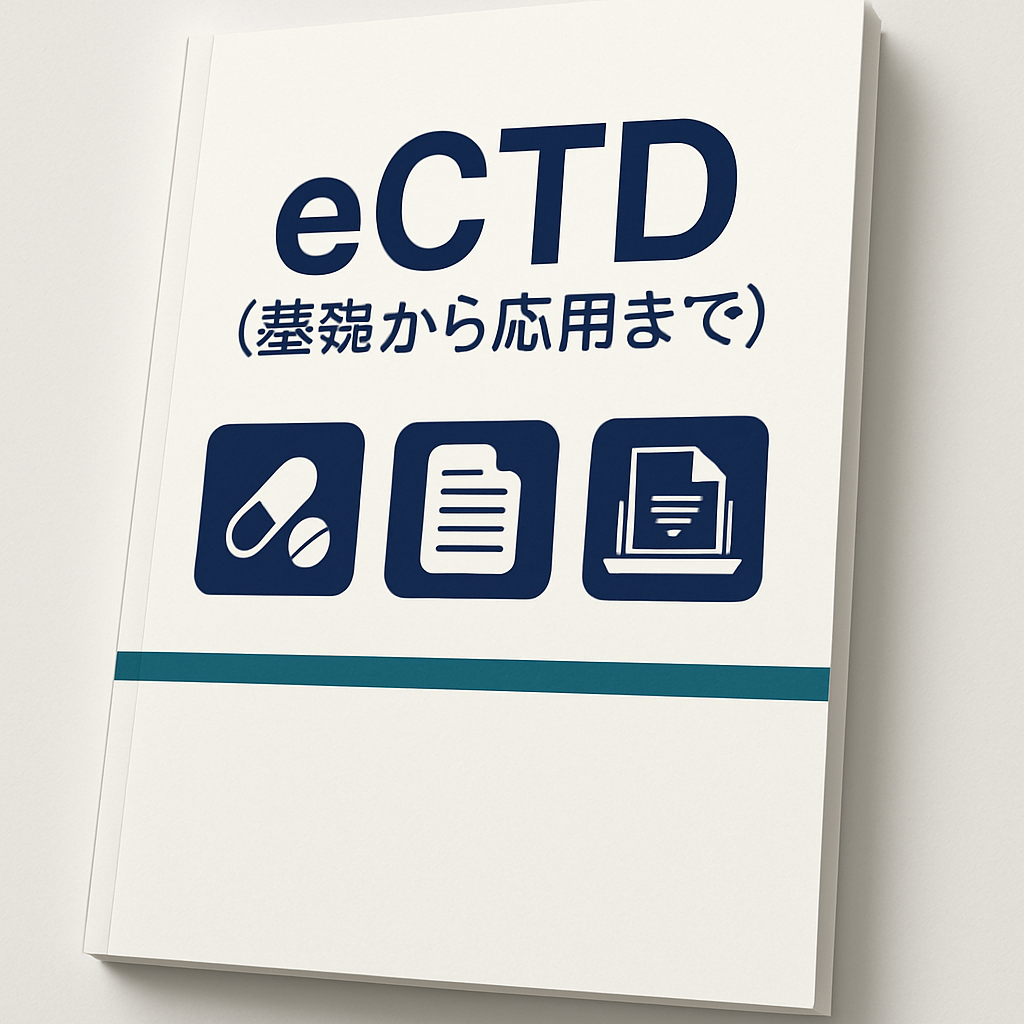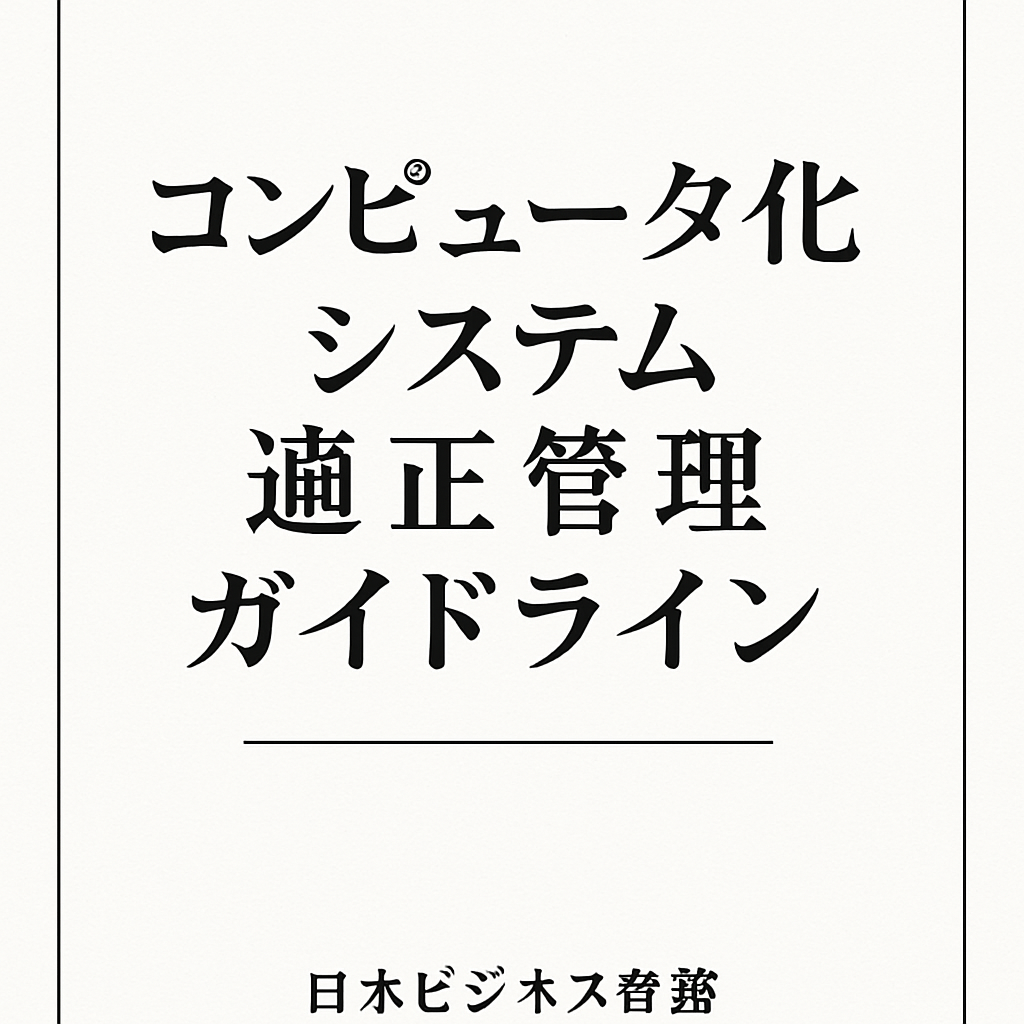書籍
専門書籍一覧
[書籍] 【製本版+ebook版】 実務担当者が抱える悩みへ回答! 『信頼性基準適用試験での実施基準【Q&A集/SOP例】』
実務担当者が抱える悩みへ回答!『信頼性基準適用試験での実施基準【Q&A集/SOP例】』
判断の悩ましいQ&A(86問) / SOP等文書作成 / 委託試験指摘事例
(WEBブラウザ上、または専用アプリケーション「bookend」より閲覧頂けます)
※購入者以外に最大9アカウントまで追加可能(無料)
~ 試験の信頼性確保は「どこまで」やれば良いのか? ~
自社の施設の信頼性確保は、過度ではないか?一般にはどうしているのか。
また申請用データとする場合、大学や海外施設で実施の場合にも適切な管理が求められる
実施体制・担当者教育から記録管理・資料保存、日本と海外の品質文化の違い、生データ管理等、
信頼性の基準適用試験に関する陥りがちな疑問点について
Q&A形式、文書作成例・指摘事例の提示にて分かりやすく解説!
本書のポイント
- 判断の悩ましい疑問点(86問)へのQ&A / 委託試験の指摘事例・考察(19事例)
具体的な実施基準が無く、企業側の判断に委ねられる非GLP試験について、実務担当者に悩まれがちな疑問点にQ&A形式をメインに分かりやすく回答 - SOP・試験計画書/試験報告書の作成ポイント
信頼性の基準適用に関するSOP・試験計画書・試験報告書の作成について一部は作成例を示しながらポイントを解説 - 生データの定義・保存や紙記録/電子データの取り扱い
非GLP試験において生データが電子データの場合、どのように考えるべきか?昨今指摘が増えている生データ関連の運用について再確認 - 海外施設に試験委託する際の信頼性の考え方
日本独自の要求事項である「信頼性基準」の試験委託についてどのように考えるべきか?海外施設へ信頼性基準適用試験を委託した際に直面する課題等にも言及
こんなことがわかる!(一例)
- GLPと同様、信頼性の基準でも信頼性保証の組織を置く必要があるのか?
- 複数の信頼性保証責任者の設置は一般的であるか?
- 申請用試験に対し、GMPの品質保証部門が照査した場合どのような認識となるのか?
- モジュール3用報告書に対する信頼性保証陳述書は発行が必要?
- 委託施設調査時、委託元の信頼性保証部門の関与必要はどの程度か?
- 「60の労力で90点取得」を実現できる効率的な方法論等はあるのか?
- 信頼性保証部門の担当者レベルを合わせるために効果的な教育法とは?
- マイクロピペットの点検頻度はどの程度で行えば良い?
- 国内外委託試験施設の調査や選定:適格性について知るには?
- 試験終了後の残余試験物質、残余標準物質等の取り扱いは?
- リモート調査における留意事項や注意点は?
書籍構成
-
第1部:信頼性基準適用試験における陥りがちな疑問点:Q&A
申請資料の信頼性の基準の適用を受ける非GLP試験においては、GLP試験のように具体的な実施基準がなく、基準を遵守するための手段も一様ではありません。そのため、試験の信頼性確保においてどこまでやれば良いのか、業務を実施する中でも悩まれている施設は多いと思われます。本項では、非GLP試験(薬効薬理試験を中心に)を実施する際に陥りがちな疑問点について、解決法を考えてみたいと思います。
目次詳細:
1. 施設の運営と組織の構成
- Q1:GLPと同様、信頼性の基準でも信頼性保証の組織を置く必要があるのか?
- Q2:複数の信頼性保証責任者の設置は一般的であるか?
- Q3:申請用試験に対し、GMPの品質保証部門が照査した場合どのような認識となるのか?
- Q4:モジュール3用報告書に対する信頼性保証陳述書は発行が必要?
- Q5:委託施設調査時、委託元の信頼性保証部門の関与必要はどの程度か?
- Q6:「60の労力で90点取得」を実現できる効率的な方法論等はあるのか?
- Q7:信頼性保証部門の担当者レベルを合わせるために効果的な教育法とは?
2. 人員および教育訓練
- Q8:信頼性基準対象となる申請資料を作成する上で特に重要とされる実施部門の役割とは?
- Q9:実施部門等の担当者に対する教育訓練方法として推奨できる方法とは?
- Q10:どのような記録を保管しておくと申請時に有益か?
- Q11:試験責任者(試験実施責任者、担当者)任命権限は誰が持つべきか?
- Q12:試験責任者の要件として最低限必要な資格・能力は?
3. 施設・装置管理
- Q13:毒劇物管理、廃棄物処理等の規程も信頼性基準の対象となるのか?
- Q14:装置の点検頻度はどの程度が適切か?
- Q15:マイクロピペットの点検頻度はどの程度で行えば良い?
- Q16:アニマルケージは装置扱いになるか?
- Q17:電子データが適切に保存できているかの確認の方法は?
4. 試験計画書
- Q18:「試験計画書」の要否の判断基準はどのように考えるか?
- Q19:スクリーニング試験の計画書の範囲はどこまで記載すれば良いか?
- Q20:記載すべき項目として最低限考慮しておくべき項目は?
- Q21:試験計画書の改訂の頻度を減らすことは可能か?
- Q22:いわゆる測定(アッセイ)する試験においても計画書は必要か?
5. 標準操作手順書(SOP)
- Q23:SOPはどのような場合に必要か?
- Q24:SOPとWorkbook等との関係はどのように整理されるべきか?
- Q25:基準書(規格書)、作業指図書、手順書、マニュアルとの違いは?
- Q26:既存の設備・装置等の取扱説明書をSOPの代用として用いることは可能か?
- Q27:SOP改訂時の留意点について
6. 試験系(実験動物・試薬など)
- Q28:薬効薬理試験における試験系として、市販の実験動物はそのまま使用できるか?
- Q29:受領試験(入荷試験)の実施方法はどうするべきか?
- Q30:動物受入時の検査はどこまですれば良いか?
- Q31:試薬管理として最低限必要な要素は何か?
- Q32:試験で使用する動物購入先への監査等は必要か?
7. 生データ管理
- Q33:生データとは?
- Q34:測定機器からの出力結果の扱いはどのようにすべきか?
- Q35:分析機器に保存されているデータの保存期間はどの程度であれば良いか?
- Q36:実験ノートの保管方法、保管期間はどうあるべきか?
- Q37:生データの修正方法について
8. 報告書(分析結果)
- Q38:試験報告書への添付資料は何をつければ良いか?
- Q39:報告書発行後の訂正はどうあるべきか?
- Q40:信頼性基準対象の試験と対象外の試験を1つの報告書にまとめる場合の留意点は?
- Q41:論文形式で記載した試験報告書を申請資料として提出する場合の留意点は?
- Q42:業績を発表した学術論文を申請資料として提出する場合の留意点は?
9. 記録の保存
- Q43:試験終了後の残余試験物質、残余標準物質等の取り扱いは?
- Q44:記録保存期間について(中止開発品を含む)
- Q45:資料保存に関する信頼性の基準と会社法および電帳法との関係は?
- Q46:記録保管庫は厳重に施錠管理が必要か?
- Q47:電子記録の保存方法としてPDFでの保存は問題ないか?
-
第2部 信頼性の基準適用試験(構造解析分野)における信頼性の基準適用への対応
~SOP,試験計画書,報告書作成時の留意事項~第2部では,受託分析会社の構造解析分野の業務を念頭に,信頼性の基準適用に関する標準操作手順書(SOP:Standard Operation Procedure),試験計画書,試験報告書の作成時の留意事項について,一部は作成例を示しながら筆者の私見を述べています。
目次詳細:
1. はじめに
2. 信頼性の基準適用試験を実施する際の前提条件
3. 構造解析分野のSOP作成の留意事項
- 3.1 標準操作手順書の管理
- 3.2 信頼性の基準適用試験の実施
- 3.3 試験計画書の作成
- 3.4 試験報告書の作成
- 3.5 生データの取り扱い
- 3.6 試験関係試料及び資料の保存
4. 構造解析分野の試験計画書作成の留意事項と作成例
- 4.1 試験計画書の記載項目
- 4.2 記載項目のうち,最低限必要な項目
- 4.3 試験計画書作成の留意事項
- 4.4 試験計画書作成例
5. 構造解析分野の試験報告書作成の留意事項と作成例
- 5.1 試験報告書の記載項目
- 5.2 記載項目のうち,最低限必要な項目
- 5.3 試験報告書作成の留意事項
- 5.4 試験報告書作成例
6. まとめ
-
第3部:信頼性基準適用試験の試験施設への委託と監査(Q&A及び事例/考察)
目次詳細:
第1節 受託施設への委託時に悩まれがちな事項:Q&A
- Q48:国内外委託試験施設の調査や選定:適格性について知るには?
- Q49:施設選定調査時に役に立つチェックリストはあるか?
- Q50:委受託契約書に盛り込むべき事項は?
- Q51:試験委託時の確認事項や注意点は?
- Q52:CRO等への委託時のQC項目と手法のすり合わせ方法は?
- Q53:受託者は監査を拒絶できるか?
- Q54:日本企業が海外の受託者へ委託する場合の特有の問題は?
- Q55:委託試験(海外を含む)における効率的な資料受領方法は?
- Q56:日本と海外での品質文化・考え方の違いにどう対応するか?
- Q57:委託試験のデータに問題があった場合の対応方法は?
- Q58:受託施設の試験責任者が試験中に変更になった場合の対応は?
- Q59:CTDの作成に当たり、CROからのデータの転記ミスを防ぐ方法は?
- Q60:受託者側のSOP等が変更された場合の対応は?
- Q61:リモート調査における留意事項や注意点は?
- Q62:モニタリングとQA監査の違いは?
- Q63:申請者側としてフォローアップ活動はどこまですべきか?
- Q64:複数のCROに同じ試験を依頼する場合の留意点は?
第2節 海外(米国等)の受託施設へ試験委託する場合の留意点:Q&A
- Q65:海外のCROの信頼性調査の効率的な方法とは?
- Q66:選定時のチェックポイントの最重要事項は?
- Q67:海外のCROへの調査訪問で、行き先や時期はどのように決めるべきか?
- Q68:海外の受託施設と日本の受託施設の異なるポイントは?
- Q69:どの程度調査すれば信頼性として申請資料に耐えうるか?
- Q70:FDA査察を受けているCROであれば必要十分と言えるか?
- Q71:米国のCROが査察を受ける申請用試験とそうでない試験との違いは?
- Q72:米国試験受託施設への調査はどのような体制で行くべきか?
- Q73:試験に関する質問はどのようにまとめておくべきか?
- Q74:英語による不十分なコミュニケーションを補完する方法は?
- Q75:海外CROの選定にコンサルタントを使うメリットは?
- Q76:海外CROと信頼性の基準に関する議論を行う上での留意点は?
- Q77:事前検討調査ではどのような活動をしておくべきか?
- Q78:海外CROの生データの調査のコツは?
- Q79:GLPの適用を受ける場合の依頼上の留意点は?
- Q80:SEND対応CROであることの重要性とは?
- Q81:海外からの試験報告書の信頼性はどのように担保すべきか?
- Q82:陳述書はGLPと同様の形式のものが必要か?
- Q83:品質保証部門(QA)の責任者への要求事項とは?
- Q84:教育記録はGLPと同様に必要か?
- Q85:大学や研究機関へ委託する場合の留意点は?
- Q86:大学等研究機関における信頼性保証部門の考え方は?
第3節 委託試験における指摘事例~実際の受託施設の調査訪問時での指摘事例からの考察~
- 1. 受託施設の訪問時に見られた指摘事例と解説
- 事例1: 標準物質の保管温度
- 事例2: 標準物質の管理
- 事例3: 分析に使用する試薬の管理
- 事例4: 天秤の定期点検
- 事例5: 自己点検記録(1)
- 事例6: 自己点検記録(2)
- 事例7: 装置校正
- 事例8: 温度管理
- 事例9: 装置のバリデーション
- 事例10: バリデーション試験
- 事例11: 装置校正基準(1)
- 事例12: 装置校正基準(2)
- 2. 試験資料(報告書、記録類)の監査時に見られた指摘事例と解説
- 事例13: 委受託契約
- 事例14: 計画書の記載不備
- 事例15: 不適切な記録の修正方法
- 事例16: 装置点検記録不備
- 事例17: 装置点検の実施
- 事例18: 生データの記録不備
- 事例19: 報告書記載と生データの不一致
お問い合わせ
株式会社イーコンプレス 丁田 由美
〒630-0244 奈良県生駒市東松ヶ丘1-2 奥田第一ビル102
TEL:050-3733-8134 FAX:03-6745-8626