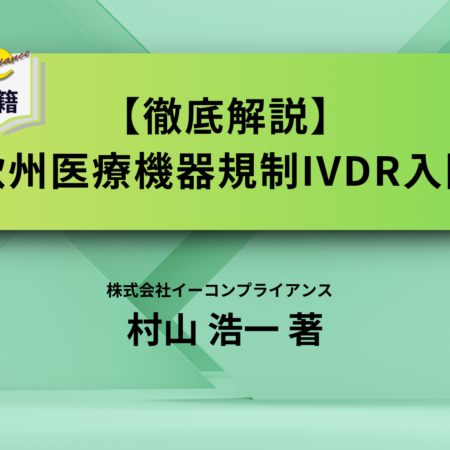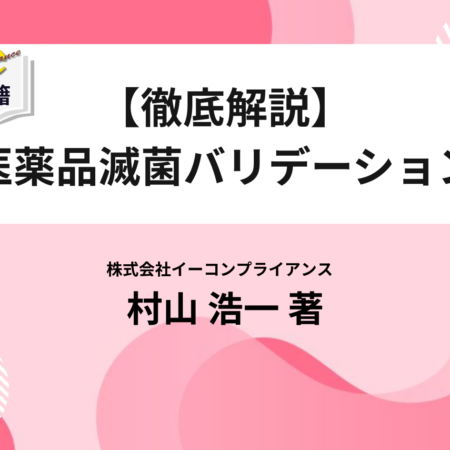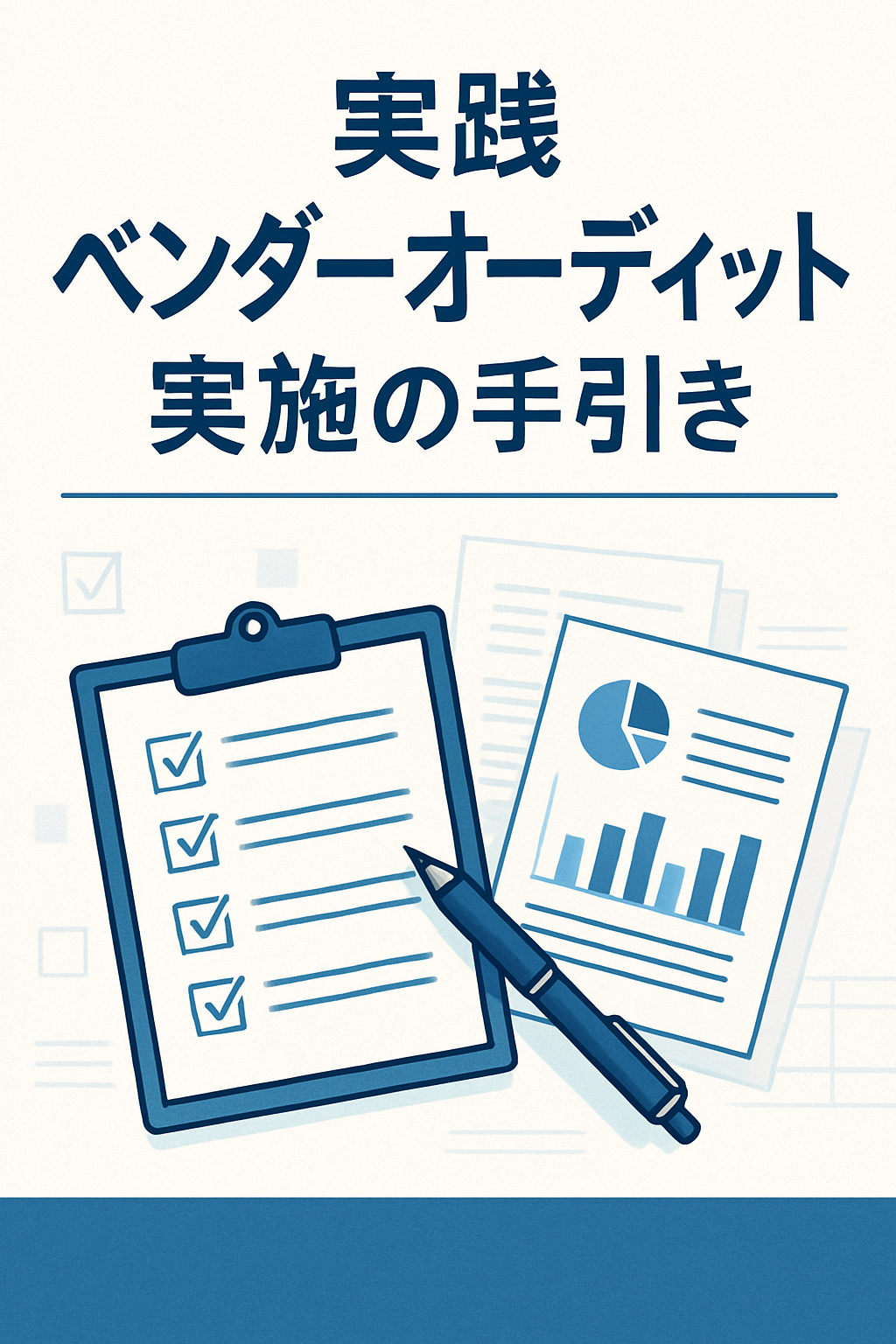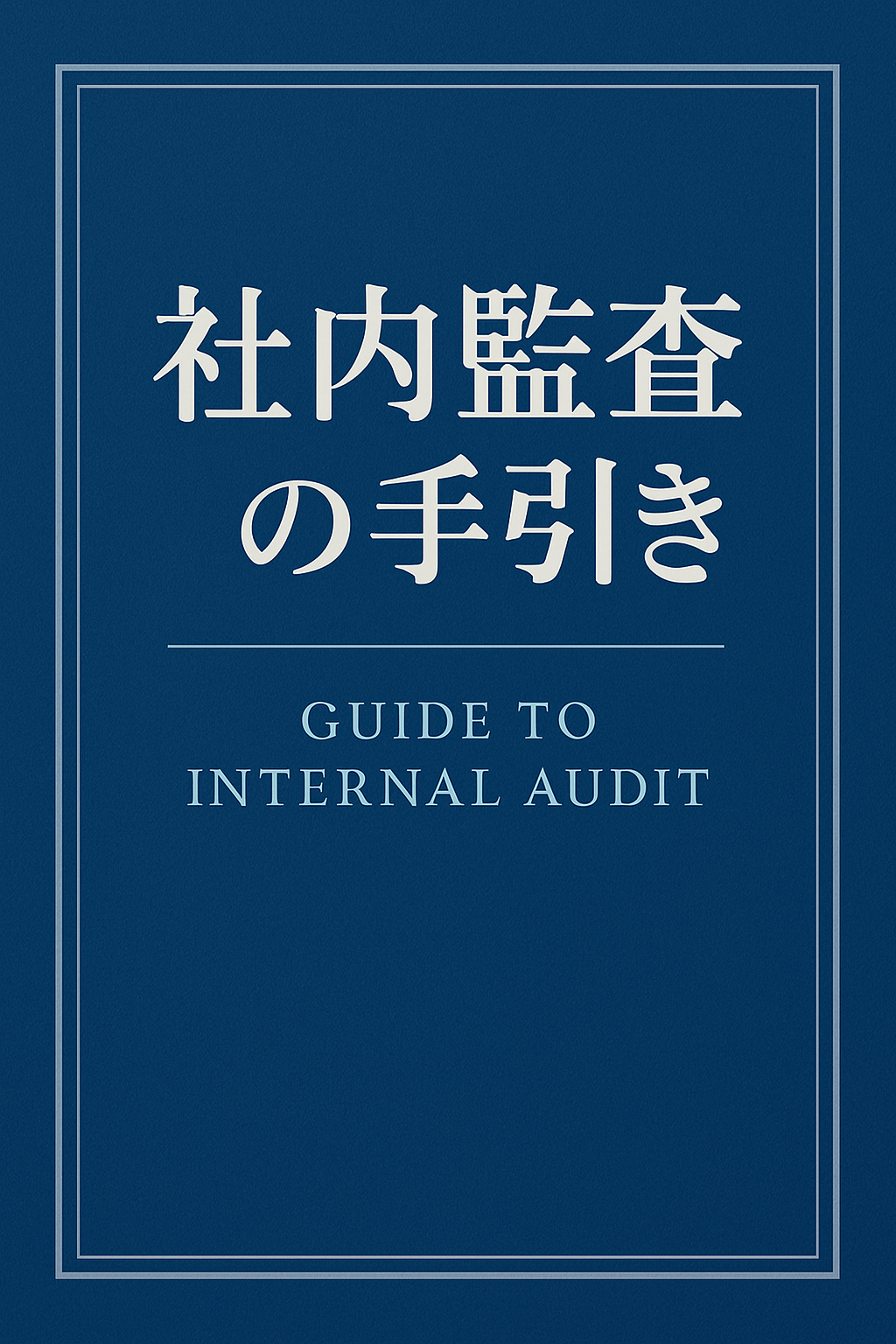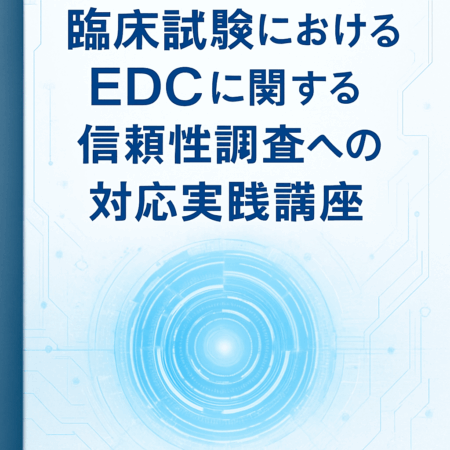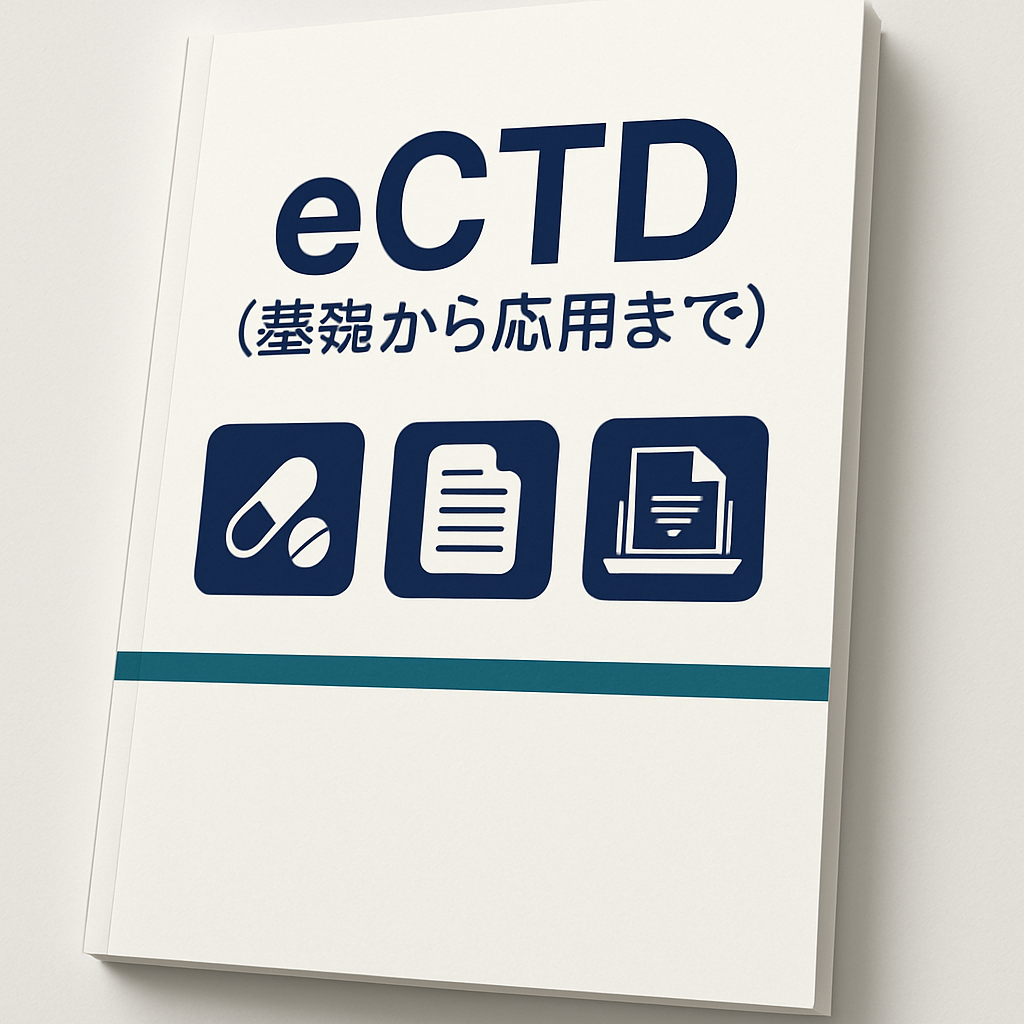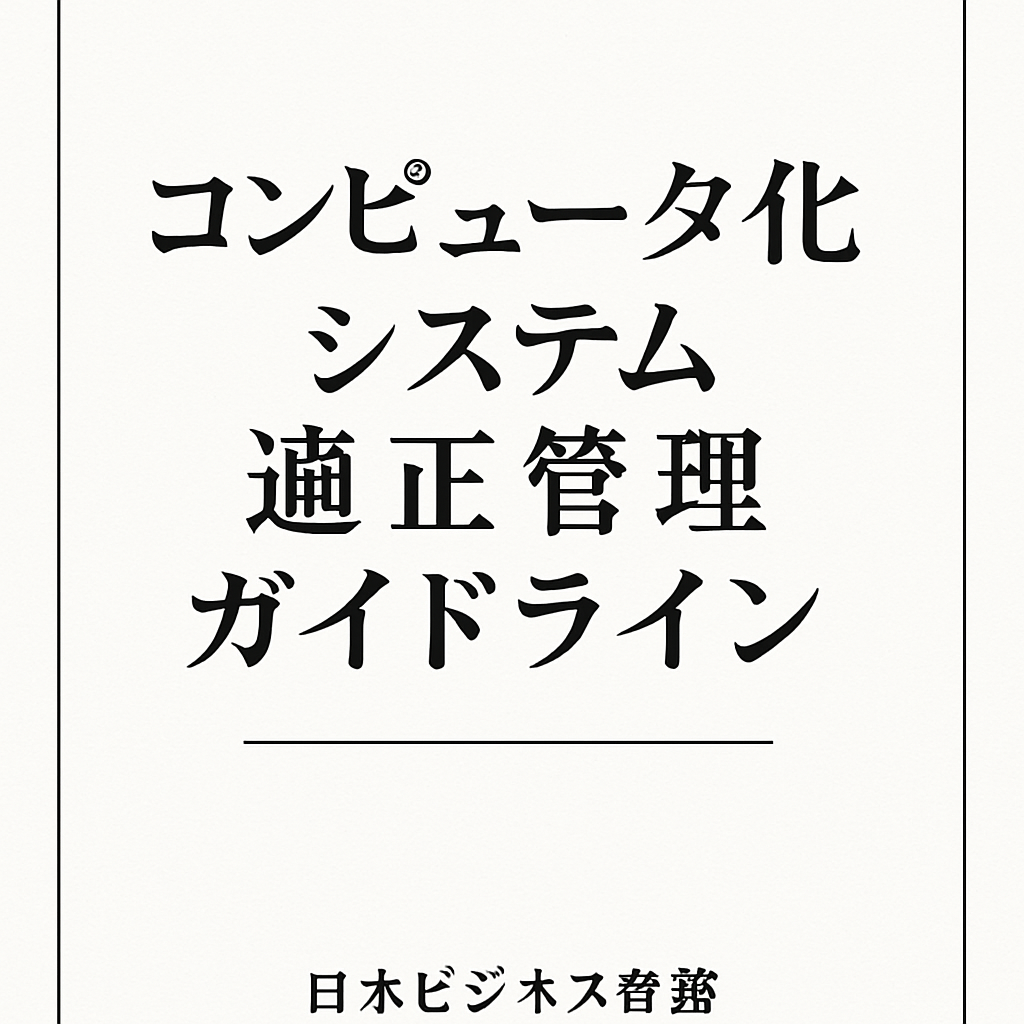書籍
専門書籍一覧
[書籍] バイオ医薬品のCTD-Q作成-妥当性の根拠とまとめ方-
バイオ医薬品のCTD-Q作成
-妥当性の根拠とまとめ方-
~規制要件に基づく、CTD M2/M3(品質パート)における各項目記載要点・記載例~
日本及び海外を見据えたバイオ医薬品開発に際し
どのような観点でCTD(品質パート)を作成すべきか
CTD M2、M3の品質パートに関する内容に焦点を当て、バイオ医薬品の開発段階毎における当局要求事項・実務面留意事項と申請資料へ提示する際の考え方を紹介!
バイオ医薬品における構造解析・特性解析、製造工程の管理、細胞基材やセルバンクシステム構築・管理、不純物の評価事例、規格及び試験方法設定、分析法バリデーション、一変申請・軽微変更時の判断規準….等々、留意すべき各項目について業界動向を踏まえた観点から、企業実務従事者・専門家陣により解説!
具体的に何を書けば良いの?申請資料へ提示する際の妥当性の根拠を示すには?CTD通知・ICH等の関連規制要件を元に、実際に記載する際の必要・不要の判断を行うためのポイントを解説!
本書で学べること(一例)
| 発刊日 | 2018年1月30日 |
|---|---|
| 体裁 | B5判並製本 171ページ |
| 価格(税込) | 49,500円 (本体45,000円+税4,500円) |
| ポイント還元 | 会員の方にはポイントを差し上げます。 ポイントは、セミナーや書籍等のご購入時にご利用いただけます。 |
| 発行 | 株式会社イーコンプライアンス |
| 送料 | 無料 |
本書より抜粋
<第1章「はじめに」より>
新有効成分含有医薬品の開発に占めるバイオテクノロジー応用医薬品(バイオ医薬品)の割合が増えている。バイオ医薬品上市数の増加に伴い、品質、有効性及び安全性に関する知見も蓄積されている。ICH Q8~11が発出されてから、バイオ医薬品開発においても、これらの知見とリスクマネジメントプロセスを取り入れた開発・管理体制の整備が進んでいる。
・・・(略)・・・
本章では、ICH Q8~11の考え方を基本とし、バイオ医薬品の特異事項を考慮しながら、CMC申請・CTD作成時に留意すべき事項を考察する。詳細は第2章以降を参考のこと。尚、ICH Q11は治験概要書など臨床開発段階の原薬には適用されず、承認後の変更についても取り扱っていないとされているが、CTD作成において実施されるリスクアセスメントの結果は、いずれのステージにおいても考え方の基本となると思われる・・・(本文へ)
<第2章「はじめに」より>
日本や海外におけるバイオ医薬品は,新薬(有効成分)開発のための探索研究, CMC ・臨床・非臨床分野での開発,その後の当局への治験申請・承認,さらには医薬品製造販売業者による実製造技術の開発を経て,市販承認のための申請資料が当局に提出され,承認後市販される。これらは市販後も、製造方法や製造所,分析法などの変更が行われることもある。この場合,その都度申請と承認が必要となってくる。また,各国の薬制が異なるため,製造業者は各国の薬制に従って開発を行い,承認を得なければならない。その過程において、治験申請,市販のための申請,さらには市販後の変更申請などの申請を行わなければならない。・・・(略)・・・バイオ医薬品CMC申請資料の様式は,他の医薬品と同様にICHガイドライン(ICH M4Q)に基づき,国際共通化の文書構造であるCTD様式/eCTD様式で行うことになっている。また,品質に関するCTDは,モジュール2:品質に関する概括資料およびモジュール3:品質に関する文書である。
本章では,国際的な薬制の動向に合わせながら,バイオ医薬品のCMC開発計画としての開発段階から市販後まで,承認を得るために作成するCMC申請資料に関する留意点や考え方,CTDそのものの記載内容や記載範囲に関して述べる・・・(本文へ)
目次
- 第1章 バイオ医薬品における特異事項と同等性/同質性評価
- はじめに
- 1. 全体の流れ
- 1.1 重要品質特性の特定
- 1.2 製造工程の開発
- 1.3 品質管理戦略の構築
- 2. 構造・特性解析からCQAの特定まで
- 2.1 構造・特性解析
- 2.2 リスクアセスメント
- 3. 製造工程開発及び品質管理戦略の構築
- 3.1 概略
- 3.2 製造方法及びプロセス・コントロール
- 3.3 原材料の選定
- 3.4 重要工程,重要中間体
- 3.5 プロセス・バリデーション/プロセス評価
- 3.6 同等性/同質性
- 4. 原薬の管理
- 5. 標準物質
- 6. ライフサイクルマネジメント
- おわりに
- 第2章 バイオ医薬品CMC申請資料における留意事項・品質パートの考え方
- はじめに
- 1. バイオ医薬品のCMC開発計画とCMC申請資料(CTD M2及びM3)の作成
- 1.1 国内で開発し国内で販売する場合
- 1.2 国内及び海外の両方で開発し,その両方で販売する場合
- 1.3 CMC申請資料作成時の留意点
- 2. CMC(品質)パートの記載内容
- 2.1 品質パート(原薬)の記載内容/記載範囲例
- 2.2 品質パート(製剤)の記載内容/記載範囲例
- 2.3 品質パート(その他)の記載内容/記載範囲例
- おわりに
- 第3章 バイオ医薬品における「製造方法・工程内管理」記載ポイント
- …
- 第4章 バイオ医薬品における構造解析・特性解析と申請資料への提示方法
- …
- 第5章 バイオ医薬品における目的物質由来不純物・製造工程由来不純物の分析/評価事例と記載方法
- …
- 第6章 バイオ医薬品における「規格及び試験方法」設定時の考え方と提示方法
- …
- 第7章 バイオ医薬品における分析法のライフサイクルマネジメントと分析法バリデーションの実施
- …
- 第8章 マスター・セル・バンク/ワーキング・セル・バンクの管理とCTD記載ポイント
- …
- 第9章 バイオ医薬品における一部変更承認申請・軽微変更時の判断・記載の注意事項
- …