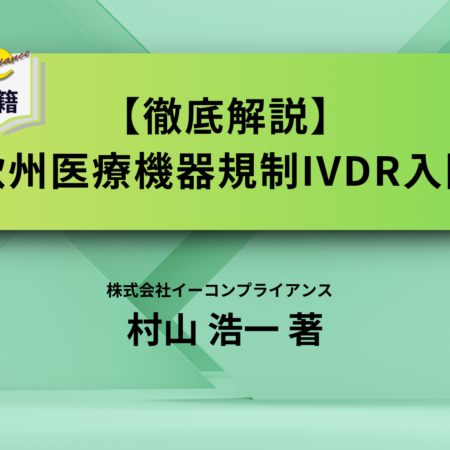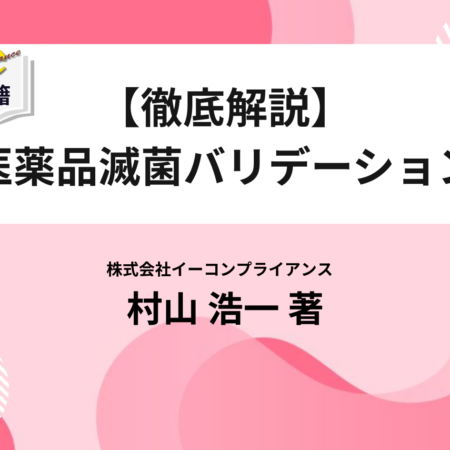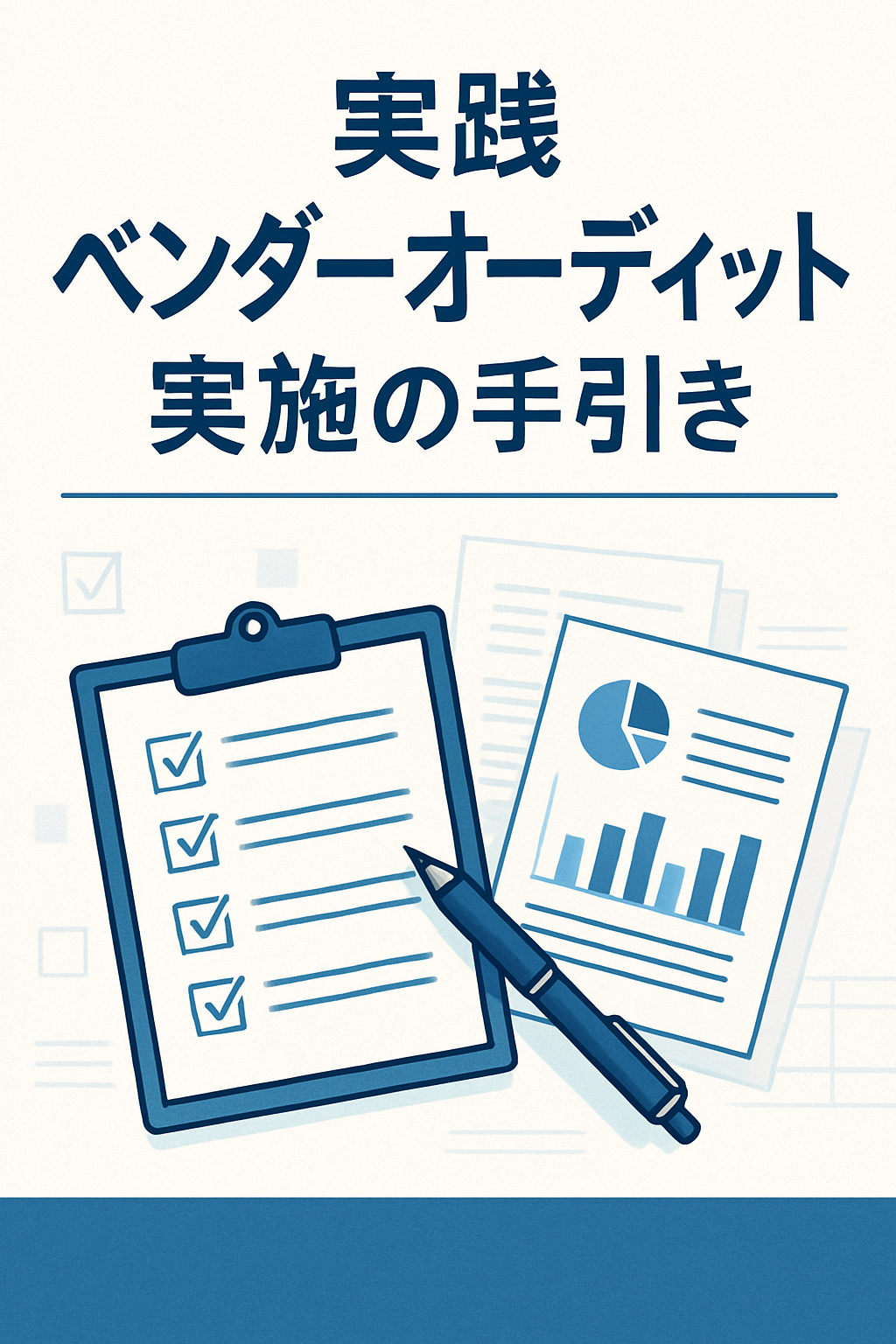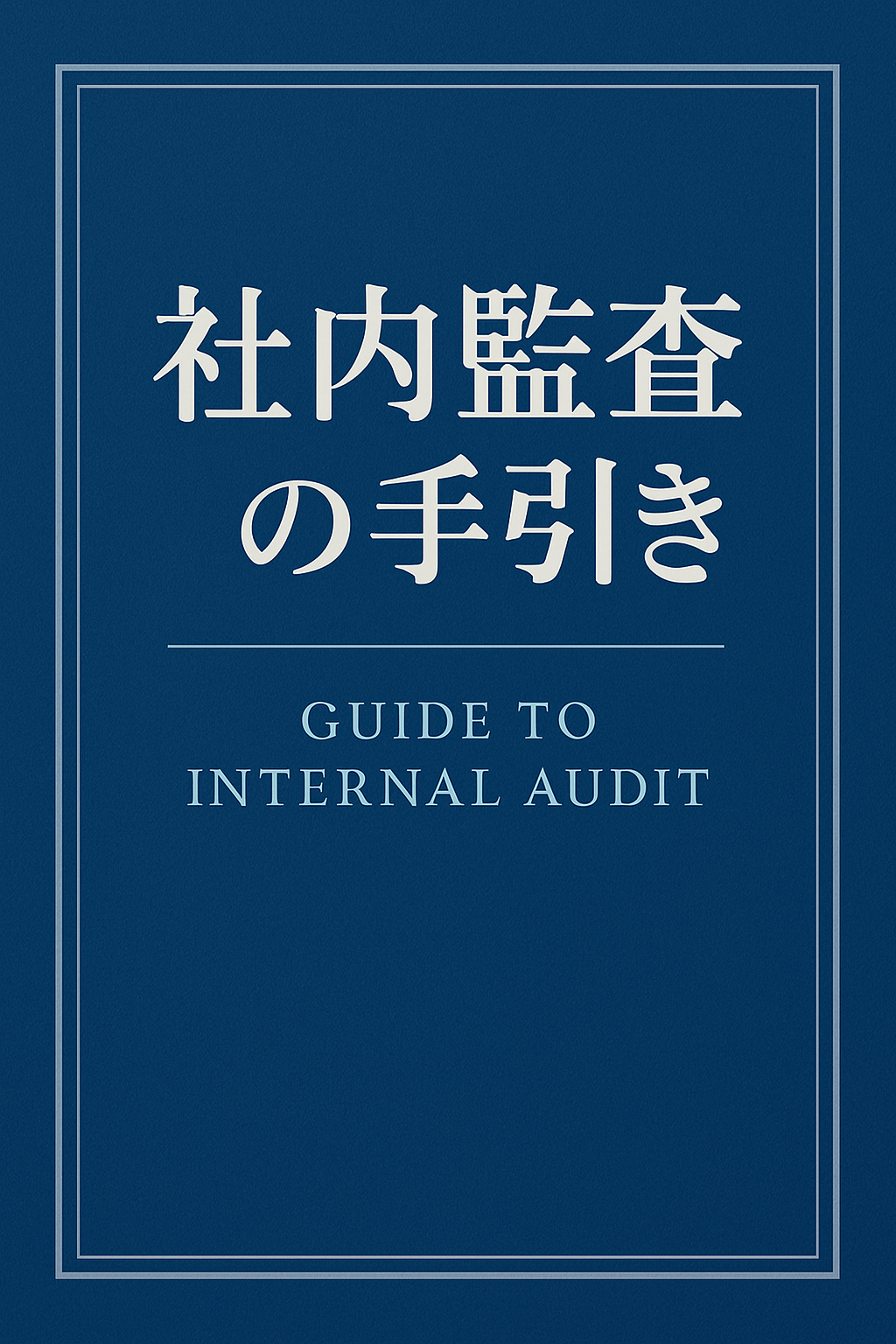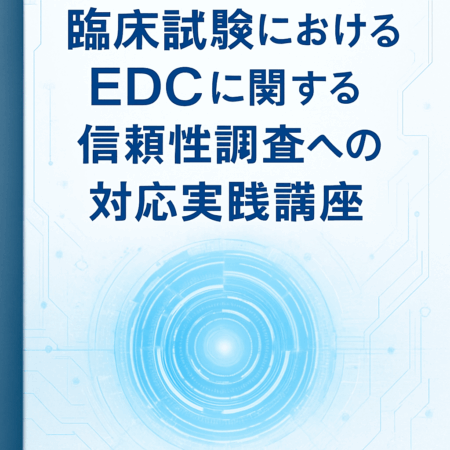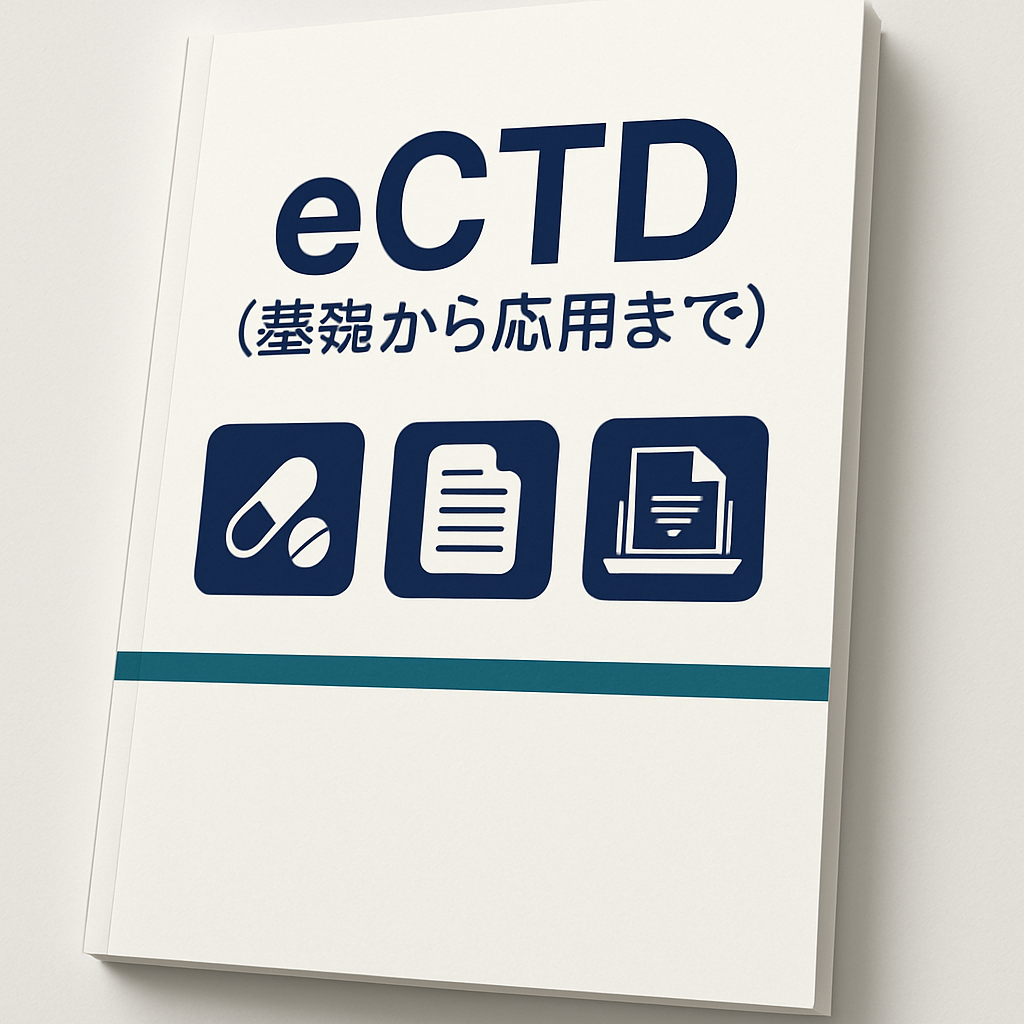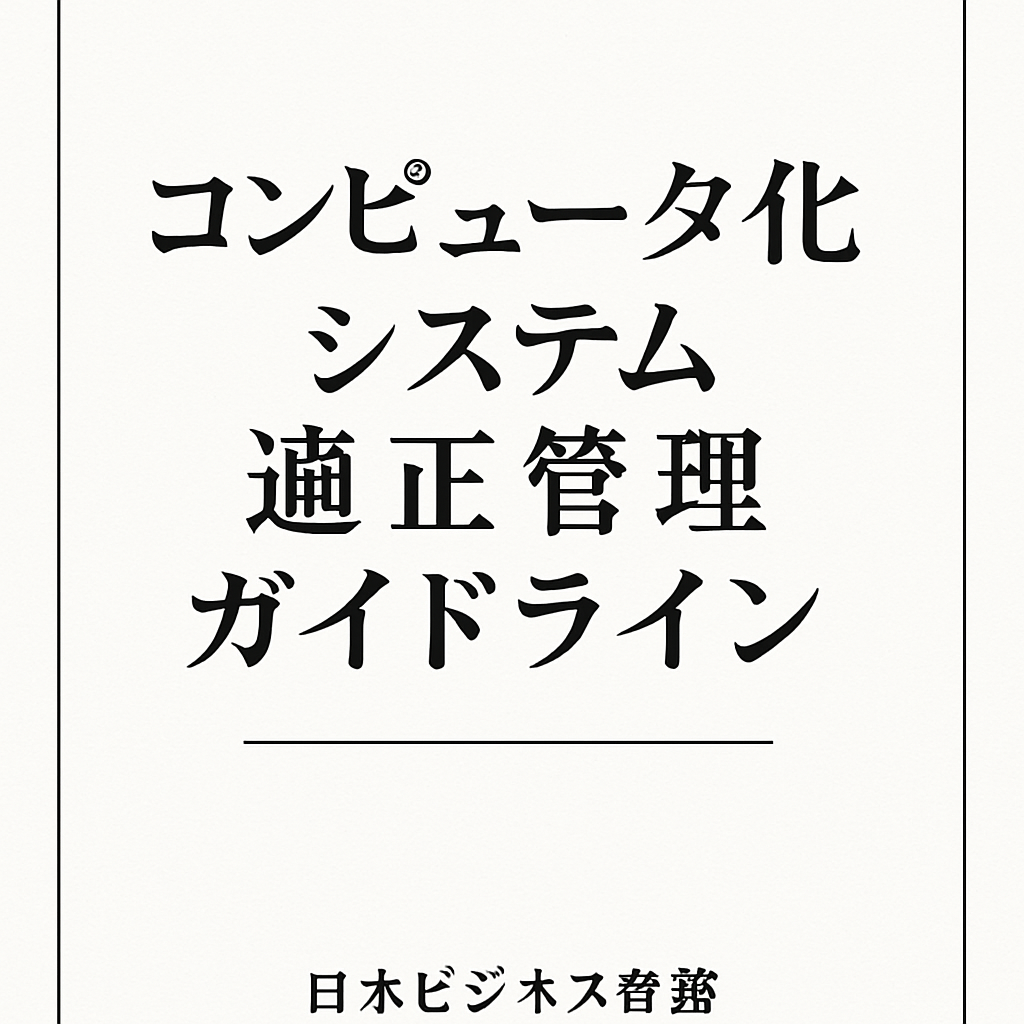書籍
専門書籍一覧
[書籍]<バイオCTDシリーズ2> バイオ医薬品(抗体医薬品)CTD-CMC記載の要点
<バイオCTDシリーズ2>
バイオ医薬品(抗体医薬品)CTD-CMC記載の要点
抗体医薬品の品質評価のためのガイダンス並びにPMDA審査報告書をふまえた
本邦特有のCTD-CMCの記載方法と妥当性を考慮した記載の要点
抗体医薬品
CTD
CMC
製造販売承認申請
★在宅中でも部署内で共有可能★
最大10アカウントまでダウンロード可能!在宅中でも、通勤途中でも、打ち合わせ先でも、スマホ・タブレットでも読める多人数閲覧型の技術専門書籍【ebook(電子書籍)】
- アプリダウンロード不要のWEBブラウザ閲覧が可能(※オンライン環境必要)
- アプリ内閲覧の場合:一度ダウンロード後はオフラインで閲覧いただけます
- 10アカウント/10端末まで閲覧でき、社内・部署内での情報共有が容易です
本書の特徴
日本特有のCTD作成ノウハウ
日本での抗体医薬品の製造販売承認申請に提出する添付資料(CTD)の記載について、日本固有の審査と承認の問題を踏まえた解説。
PMDA審査報告書の視点
PMDA審査報告書から分かる当局の検討項目及び筆者の見解を踏まえ、照会事項を未然に防ぐための記載方法を解説。
実務的な記載例の提示
抗体医薬品のCTD-CMC作成において重要な要素について、多数の実務的な記載例と表データ例を紹介。
「バイオ医薬品CTD-Qー妥当性の根拠とまとめ方ー」に続くバイオCTD作成シリーズ【第2段】。抗体医薬品の品質評価のためのガイダンス並びにPMDA審査報告書をふまえ、本邦特有のCTD-CMCの記載方法・妥当性を考慮した記載の要点を示します。
本書の出版にあたって
業界団体から抗体医薬品を対象としたモジュール2.3モックアップが出ている一方、さらにプラスして、実際に作成する際の観点にさらに踏み込んだ記載方法を希望する声も多くあります。
※要望の一例:
- 「特性解析」:実データの解析方法や提示結果からどのようにまとめるか等の分析手法のノウハウ部分も知りたい
- 「分析法バリデーション」:検討方法や判定基準の妥当性まで言及した内容を知りたい
- 「規格の妥当性」:当局の求める、市販後を意識した “より原則的な解説” を知りたい 等
上記の観点をふまえ、実際の作成時を想定する際さらに踏み込んだ内容を網羅すべく、CTD作成の際に重要となる、「データの妥当性」を考慮した観点から記載の要点を示します!
バイオ/抗体医薬品のCTD作成において
審査担当者に十分理解してもらえるような検討項目・判断基準を満たすためには、具体的に「何を」「どの程度」記載すればよいのか?
提示するデータで審査側が理解できるかの視点まで言及し、各項目のまとめ方を詳細に解説!市販後ライフサイクルを見据えリスクアセスメントに基づいた品質の一貫性の観点から照会事項を未然に防ぐために、経験豊富な筆者が各要素を詳細に解説しています。
本書で解決できる課題
- 工程由来不純物はどのように管理すべきか
- 常用標準品と一次標準品とで異なる管理項目はどのように決めればよいか
- 確認試験(定性試験)でペプチドマップ法を利用する場合の留意事項は?
- 試験方法がふさわしいとはどのように説明するのか
- 分析法バリデーションの判定基準はどのように設定するのか
- 不純物管理方法における定量限界付近での真度と精度の確認の必要性は?
- バイオシミラーの一次構造の確認では先発との比較だけでよいのか?
商品概要
| 発売日・配信開始日 | 2020年12月24日 |
|---|---|
| フォーマット | 製本+ebook版(PDF)(WEBブラウザ上、または専用アプリケーション「bookend」より閲覧頂けます) ※このebookは印刷不可・コピー不可です。 |
| 体裁 | B5判 並製本 165頁(製本版) B5 PDF 165頁(ebook版) |
| 価格(税込) | 【製本版】44,000円 定価:本体40,000円+税4,000円 【製本版+ebook版のセット】60,500円 定価:本体55,000円+税5,500円 |
| アカウント数 | アカウント数:10アカウント ※購入者を除いた10名様でのアカウント適用を希望の場合は、申込の際の「備考欄(通信欄)」にその旨ご記入ください 閲覧可能PC数:10台/10アカウント(同一アカウントに限る) |
| 閲覧期間 | 無期限 |
| オフライン閲覧 | bookendアプリ使用の場合は可能 WEBブラウザ使用の場合はオンラインが必要です。 |
| 対応OS・デバイス | Win・Macの両OS、スマートフォン・読書端末(iPhone,iPadなど) |
目次
概要
バイオ医薬品におけるCTD-CMC M3の各要素について審査報告書での当局の視点をふまえ、筆者の観点から数多くの提示例を示す!
- 第1章 CTDの構成と記載整備の概要
日本固有の審査と承認の問題を踏まえてCTD の構成と項目毎の記載整備の概要を説明する。 - 第2章 特性解析と標準物質
製造販売承認申請書の添付資料モジュール3の「特性」とその内容に関連する「標準品又は標準物質」の記載について解説する。
◎PMDAの審査報告書から分かる当局の検討項目及び筆者の見解(「構造解析」・「不純物」・「標準物質」項)
◎分析法の各試験項目:試料調製手順,分析操作手準及び解析方法の要点
◎一次標準物質と常用標準品の2 段階の運用例 - 第3章 規格及び試験方法
同じ抗体であっても品質試験項目は同じにならず、それぞれの製造方法の一貫性及び工程管理の方法に基づいて出荷試験にふさわしい試験方法と規格を定めることになる。
◎妥当性の根拠をふまえ、抗体医薬品の試験項目毎に原薬及び製剤の規格と試験方法の記載例を提示
◎PMDAの審査報告書から分かる当局の検討項目及び筆者の見解
◎「含量(タンパク質量)」「性状」「確認試験」「示性値」「純度試験」「エンドトキシン」「微生物限度」等々、各試験項目毎に、筆者の観点から留意すべきポイントと多くの記載例を示す! - 第4章 分析法バリデーション
分析法バリデーションを実施することで,分析法の誤差が原因で生じる試験の判定の誤りの確率が,承認後の製品のライフサイクルを通じて許容できる程度であることを規制当局に対して科学的に説明することになる。
◎「確認試験」「示性値」「純度試験」「生物学的活性」「定量法」:試験法のタイプ毎の提示要件を解説! - 第5章 製造
昨今の規制当局の意向は、製造方法の管理及び順守を正確に把握できるように詳しい製造方法の記載並びに重要工程の説明や管理パラメータの根拠の提示を望んでいる。
◎原薬・製剤における各項目の記載において、多数の表データ例を紹介し、各製造工程でのプロセスパラメータ及び工程内試験の管理状況とその妥当性の根拠についての記載例を示す
著者プロフィール
関連商品
お問い合わせ