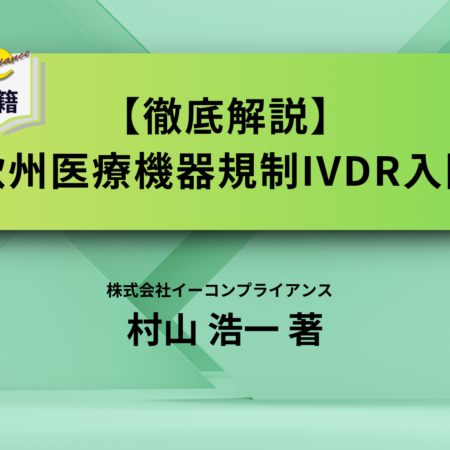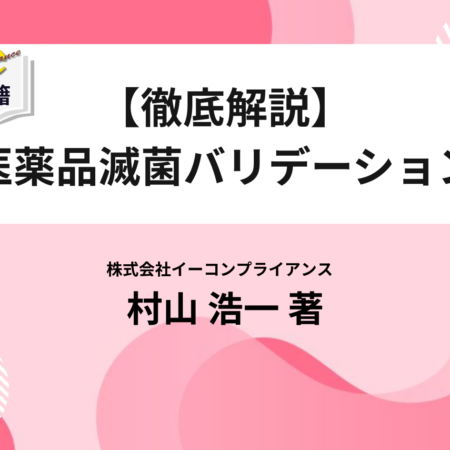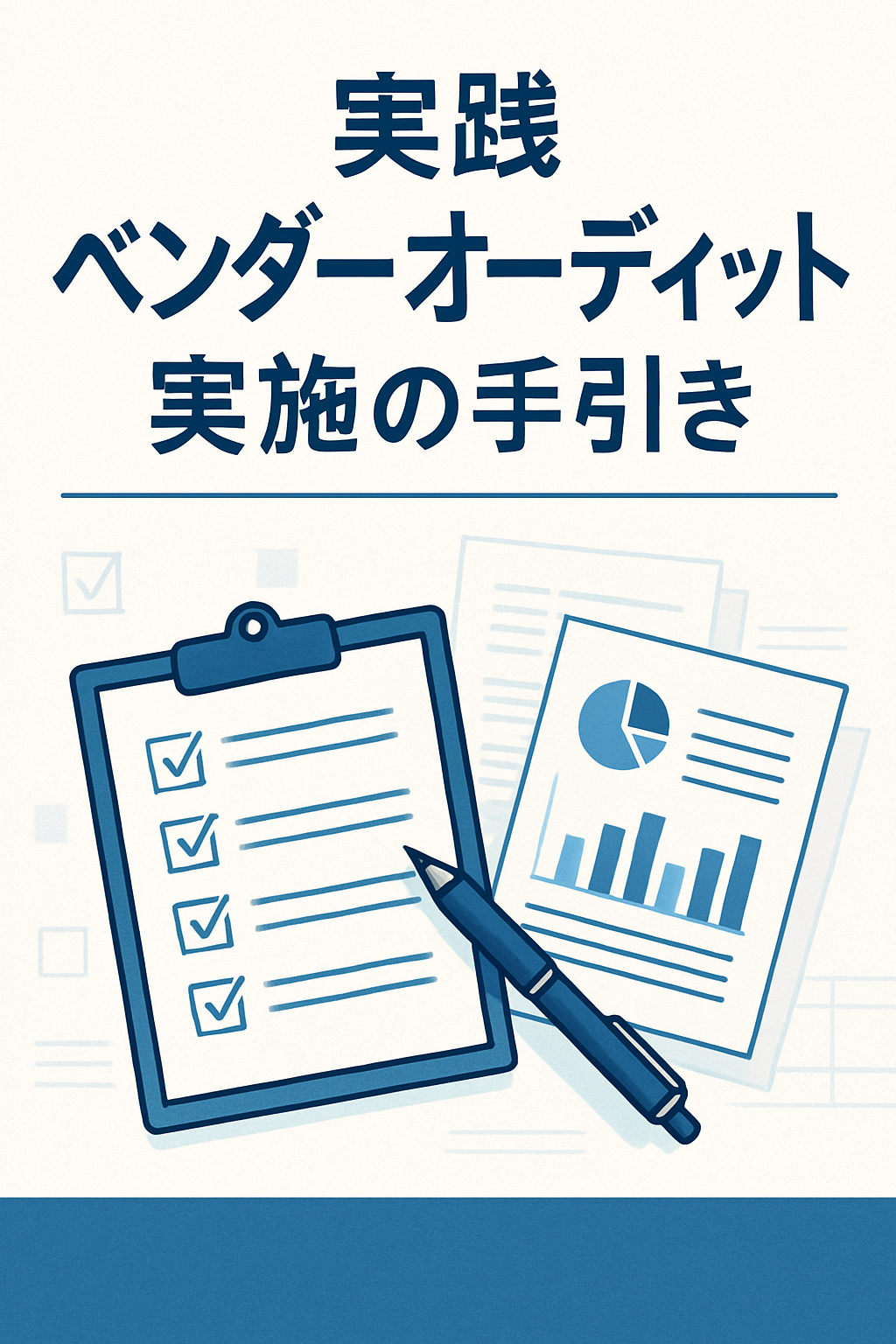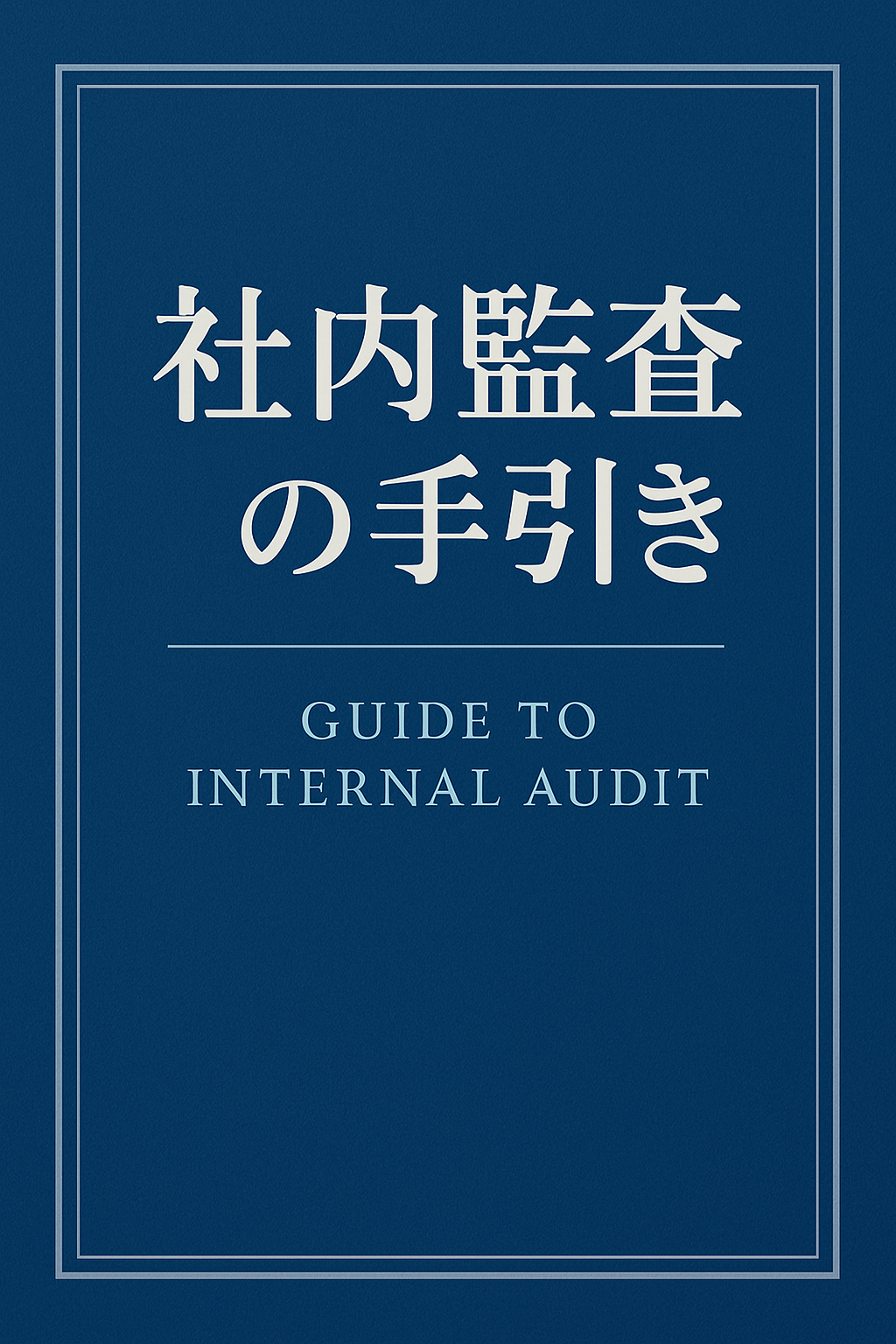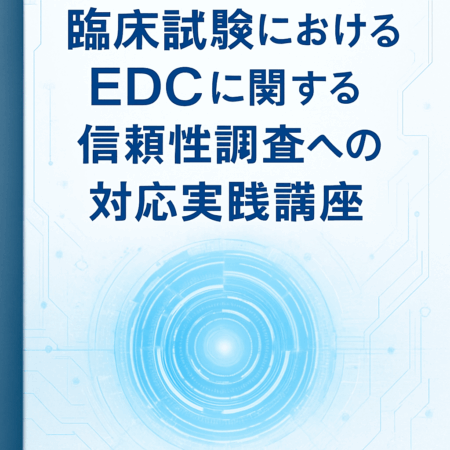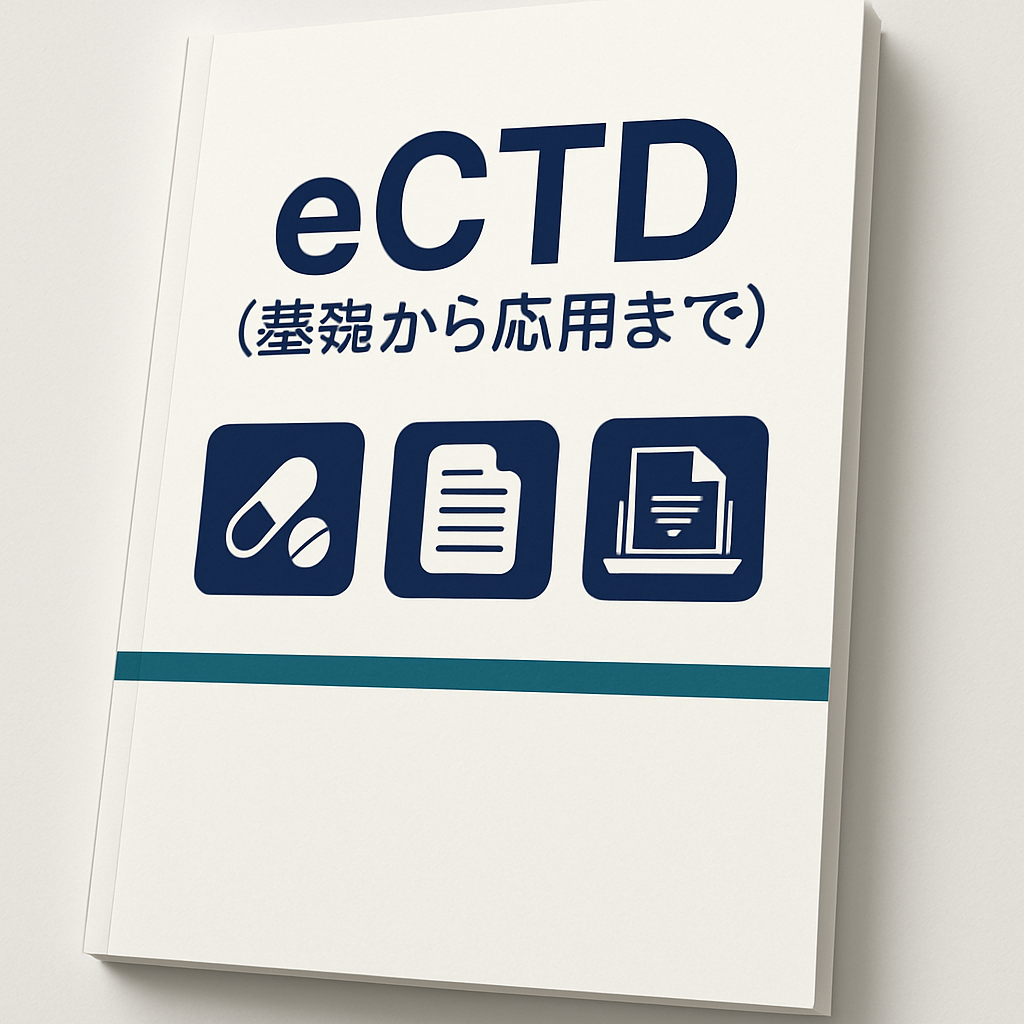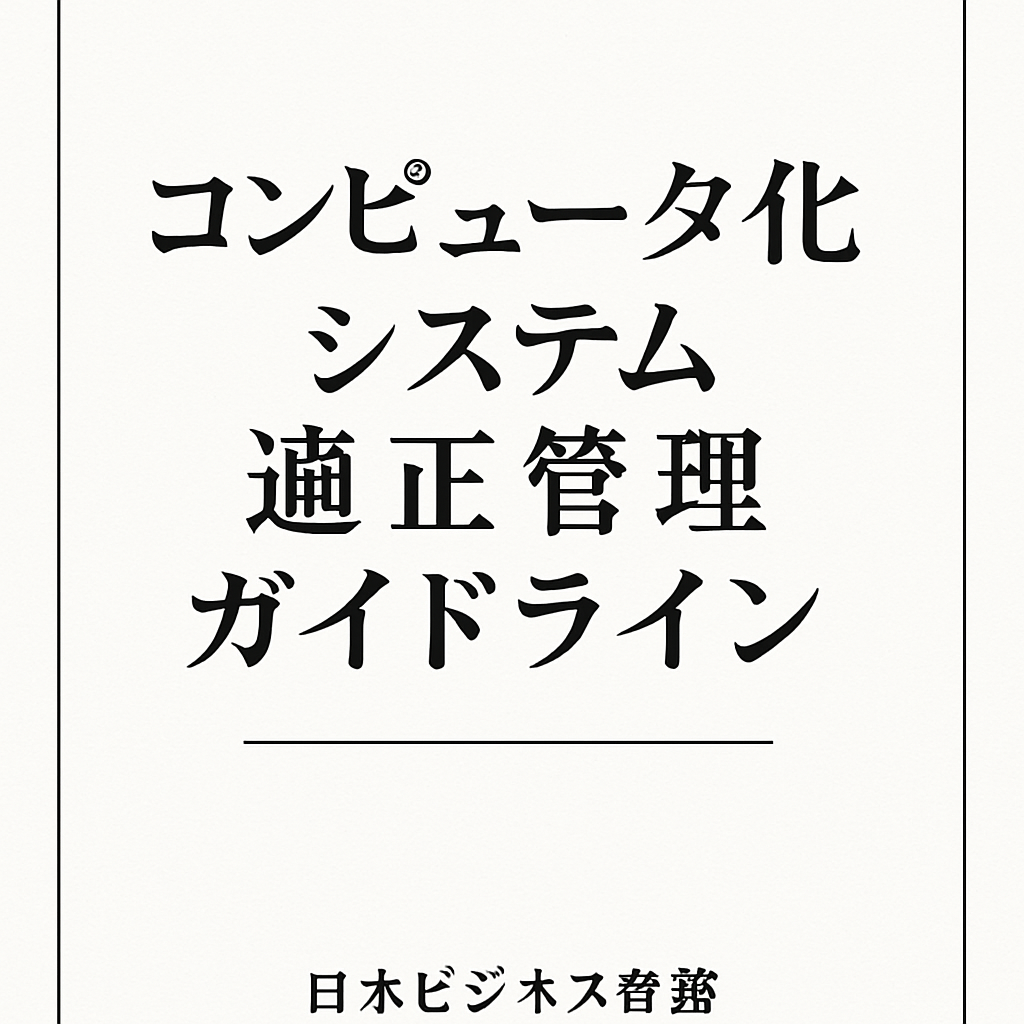書籍
専門書籍一覧
[書籍] <バイオCTDシリーズ2> バイオ医薬品(抗体医薬品)CTD-CMC記載の要点
<バイオCTDシリーズ2> バイオ医薬品(抗体医薬品)CTD-CMC記載の要点
製薬企業担当者のための実務書
<バイオCTDシリーズ2> バイオ医薬品(抗体医薬品)CTD-CMC記載の要点
~弊社既刊「バイオ医薬品CTD-Qー妥当性の根拠とまとめ方ー」に続くバイオCTD作成シリーズ!抗体医薬品の品質評価のためのガイダンス並びにPMDA審査報告書をふまえた本邦特有のCTD-CMCの記載方法と妥当性を考慮した記載の要点~
バイオ医薬品
抗体医薬品
CTD
薬事申請
品質管理
価格: 44,000円(税込)
定価:本体40,000円+税4,000円
著者紹介
本書の概要
本書では,日本での抗体医薬品の製造販売承認申請に提出する添付資料(CTD)のうち製造,特性解析,規格及び試験方法を中心とした品質管理の記載の要点について解説します。
バイオ/抗体医薬品のCTDにおいて、審査担当者に十分理解してもらえるような検討項目・判断基準を満たすためには具体的に何をどの程度記載すればよいのか?
市販後ライフサイクルを見据えリスクアセスメントに基づいた品質の一貫性の観点から照会事項を未然に防ぐために、経験豊富な筆者が各要素を詳細に解説!
欧米での治験申請では,臨床ステージ毎に原薬・製剤に関するCTDを規制当局に提出し,その都度,治験薬の臨床治験に使用することの製造管理及び品質管理の是非について審議を受けます。一方,日本では,一般的な医薬品の治験申請(治験相談)において原薬・製剤に関する製造並びに品質の詳細なデータをCTDの形式で提示することはほとんど行われておらず,製造販売承認申請時に初めてCTDを提出します。
このため,臨床期間中に確認された治験薬での有効性及び安全性に関する品質の一貫性が,承認後の市販薬でも継続して確保されることを規制当局の審査担当者に十分理解してもらえるように,CTDの記載内容を整備する必要があります。
こんなことがわかる!
- 一次構造の確認はどのように行えばよいのか?
- 工程由来不純物はどのように管理すべきか
- 常用標準品と一次標準品とで異なる管理項目はどのように決めればよいか
- 確認試験(定性試験)でペプチドマップ法を利用する場合の留意事項は?
- 試験方法がふさわしいとはどのように説明するのか
- 分析法バリデーションの判定基準はどのように設定するのか
- 不純物管理方法における定量限界付近での真度と精度の確認の必要性は?
- バイオシミラーの一次構造の確認では先発との比較だけでよいのか?
書籍構成&各章のポイント
バイオ医薬品におけるCTD-CMC M3の各要素について審査報告書での当局の視点をふまえ、筆者の観点から数多くの提示例を示します!
▼第1章 CTDの構成と記載整備の概要
日本固有の審査と承認の問題を踏まえてCTDの構成と項目毎の記載整備の概要を説明します。
▼第2章 特性解析と標準物質
製造販売承認申請書の添付資料モジュール3の「特性」とその内容に関連する「標準品又は標準物質」の記載について解説します。
- PMDAの審査報告書から分かる当局の検討項目及び筆者の見解(「構造解析」・「不純物」・「標準物質」項)
- 分析法の各試験項目:試料調製手順,分析操作手準及び解析方法の要点
- 一次標準物質と常用標準品の2段階の運用例
▼第3章 規格及び試験方法
同じ抗体であっても品質試験項目は同じにならず、それぞれの製造方法の一貫性及び工程管理の方法に基づいて出荷試験にふさわしい試験方法と規格を定めることになります。
- 妥当性の根拠をふまえ、抗体医薬品の試験項目毎に原薬及び製剤の規格と試験方法の記載例を提示
- PMDAの審査報告書から分かる当局の検討項目及び筆者の見解
- 「含量(タンパク質量)」「性状」「確認試験」「示性値」「純度試験」「エンドトキシン」「微生物限度」等々、各試験項目毎に、筆者の観点から留意すべきポイントと多くの記載例を示す
▼第4章 分析法バリデーション
分析法バリデーションを実施することで,分析法の誤差が原因で生じる試験の判定の誤りの確率が許容できる程度であることを規制当局に対して科学的に説明することになります。
- 「確認試験」「示性値」「純度試験」「生物学的活性」「定量法」:試験法のタイプ毎の提示要件を解説
▼第5章 製造
昨今の規制当局の意向は、製造方法の管理及び順守を正確に把握できるように詳しい製造方法の記載並びに重要工程の説明や管理パラメータの根拠の提示を望んでいます。
- 原薬・製剤における各項目の記載において、多数の表データ例を紹介
- 各製造工程でのプロセスパラメータ及び工程内試験の管理状況とその妥当性の根拠についての記載例を示す
株式会社イーコンプレス
担当:丁田 由美
〒630-0244 奈良県生駒市東松ヶ丘1-2 奥田第一ビル102
© 2025 株式会社イーコンプレス All Rights Reserved.
CTD-CMC記載の要点.png)