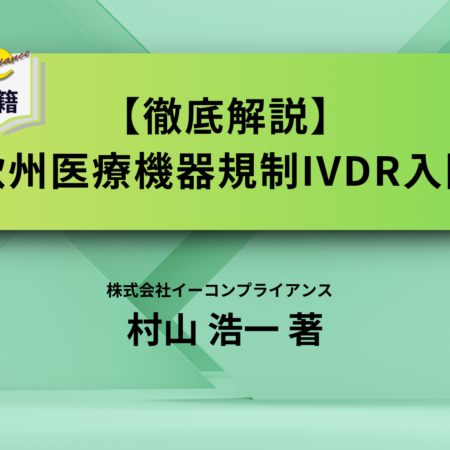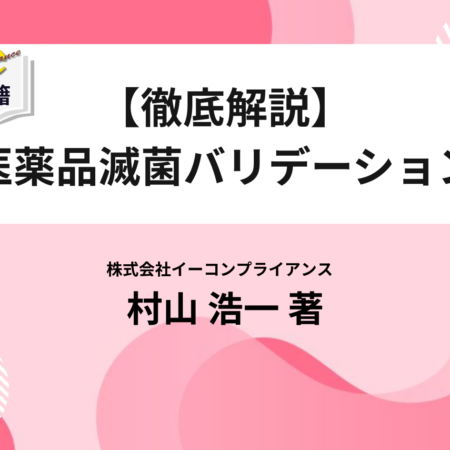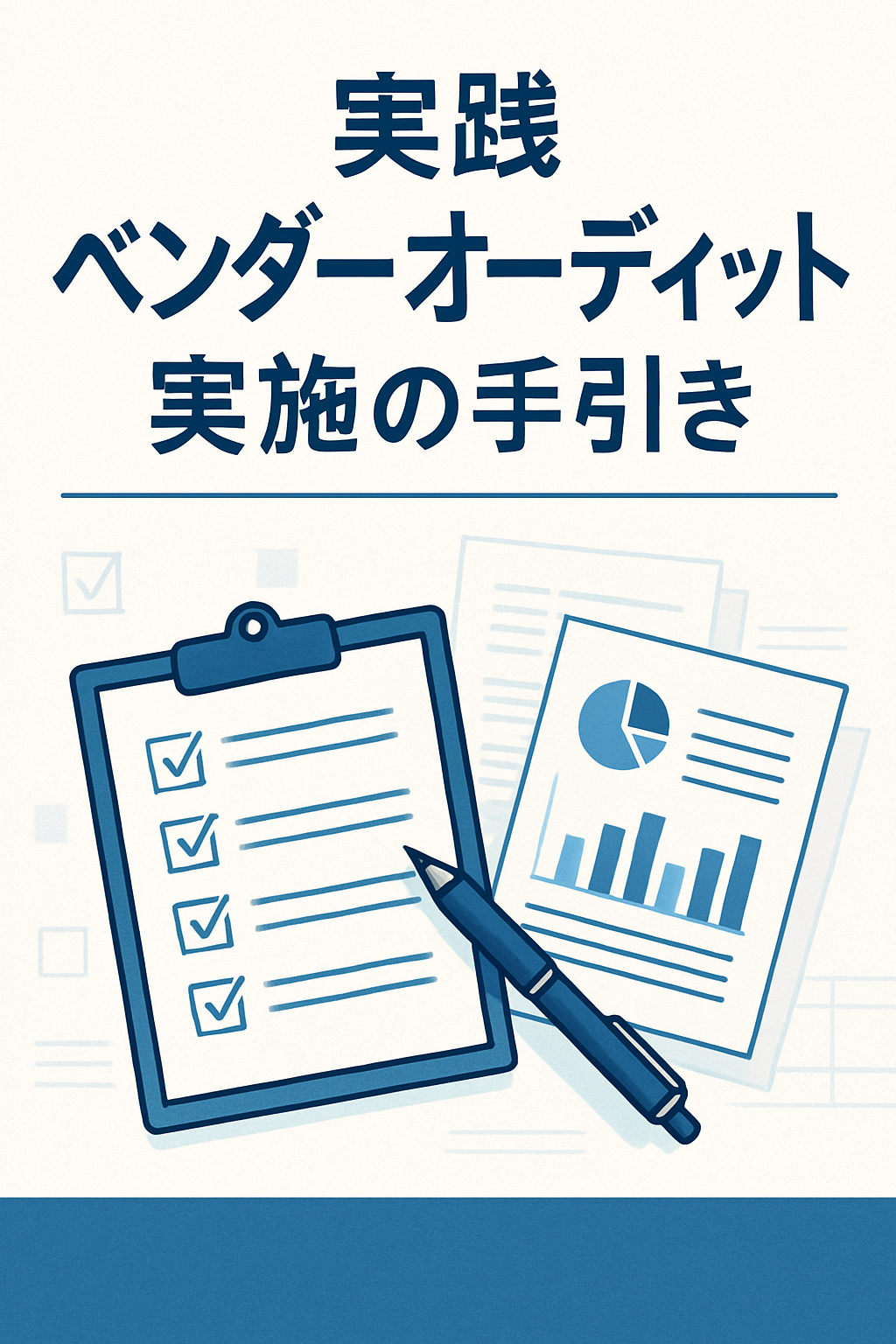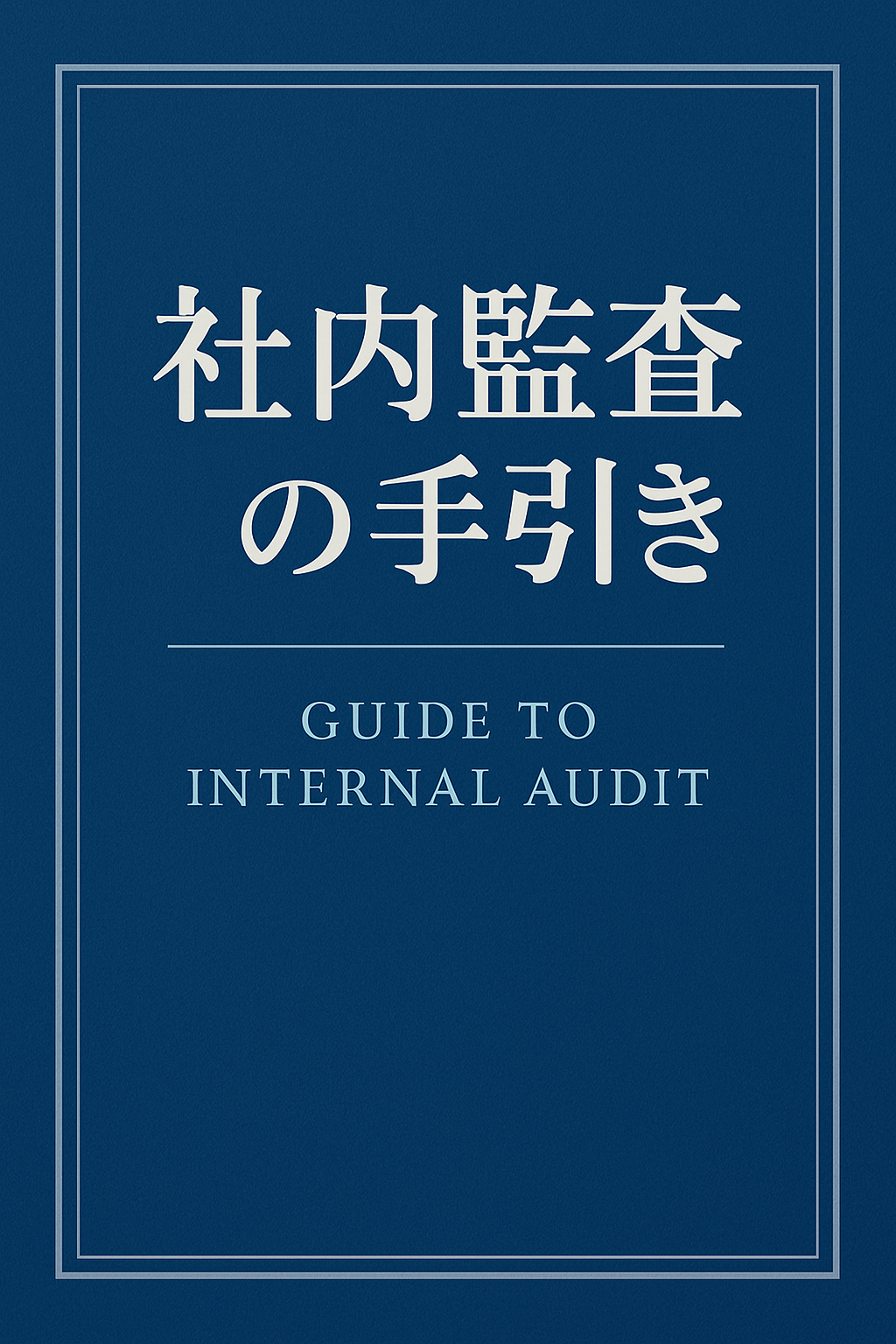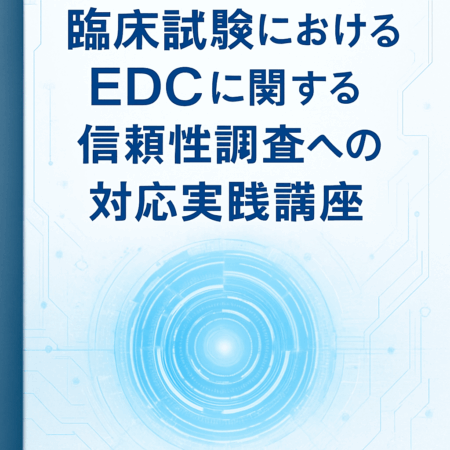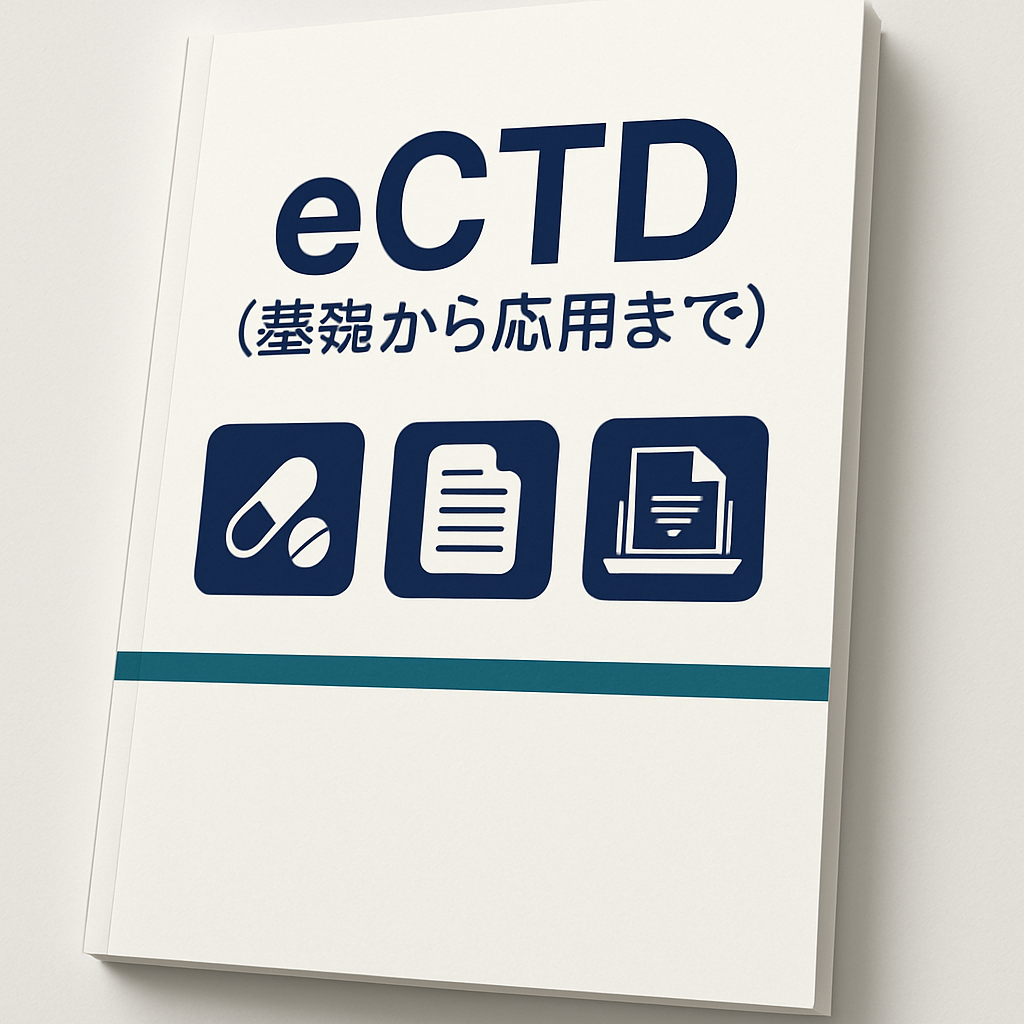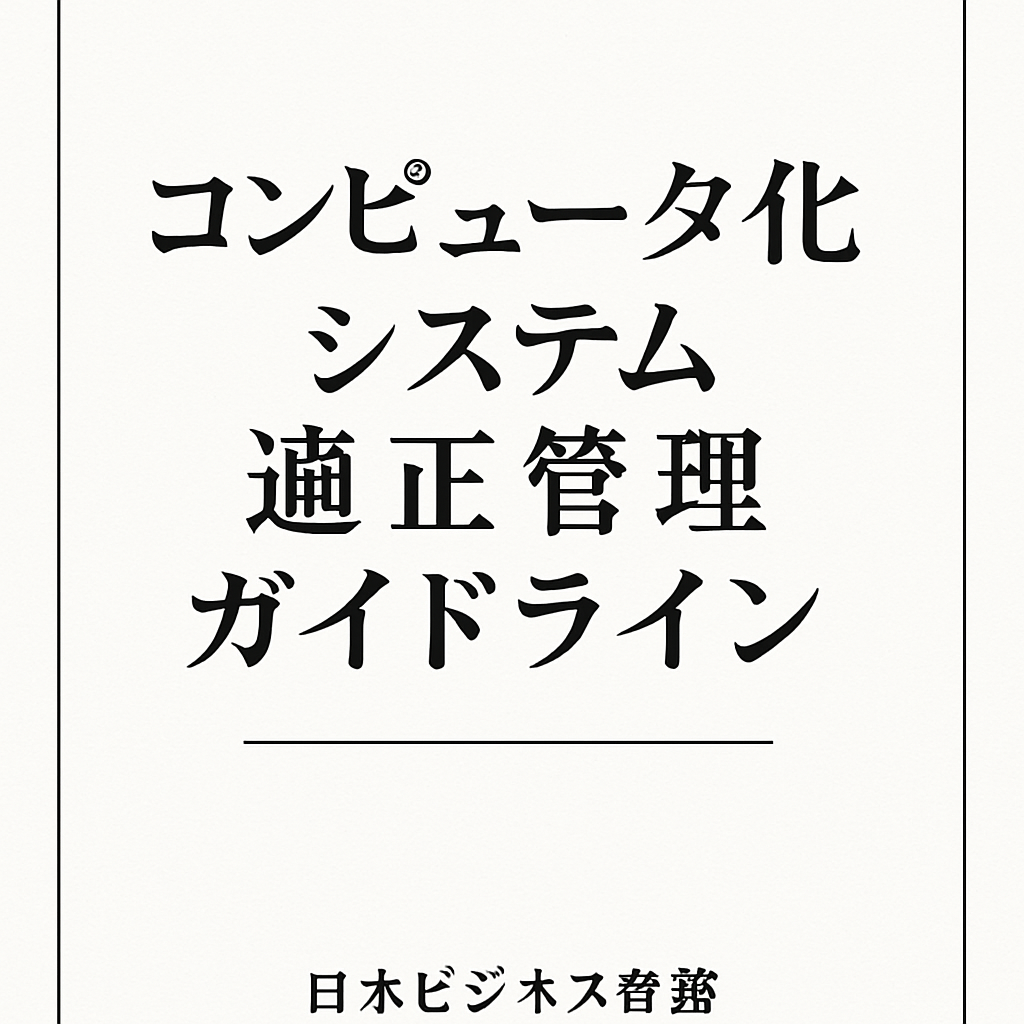書籍
専門書籍一覧
[書籍] <3極(日米欧)規制/当局の考え方の違い> [Global]治験/市販後での 安全性情報の収集・評価・報告要否と PVベンダーコントロール
<3極(日米欧)規制/当局の考え方の違い>
[Global]治験/市販後での安全性情報の収集・評価・報告要否とPVベンダーコントロール
~様々な症例・例題を通して3極の違いを紐解く/ベンダーを多用するPV体制維持に必要な信頼性保証手法~
「どういった基本的考えや姿勢によって、どこまで同じで、どこからが違うのか」を明確にする1冊
なぜ違うのか、その背景から解説するので腑に落ちる!
【製本版のみの特長】
- 表や図表が見やすく、頁をめくりながら参照しやすい
- 重要なポイントに付箋やマーカーで印をつけて自分だけの参考書に
- 会議や打ち合わせで資料として活用しやすい
- 長時間のデジタル作業で疲れた目に優しい紙の質感
※電子書籍版(ebook)との組み合わせも可能です。詳しくはお問い合わせください。
日米欧規制当局の安全管理情報に対する考え方や捉え方が、「どういった基本的考えや姿勢によって、どこまで同じで、どこからが違うのか」を明確にする1冊
日米欧で目指す安全対策とは?
日米欧では、安全対策実施に対する考え方や、それに伴う体制に関しても大きな違いがあります。安全対策実施に関し、どこに、どのような違いがあるのか、無いのか。
『治験時の安全管理情報』、『市販後の安全管理情報』
詳細に紐解いていくことで、日米欧のスタンスの違いと対応の違いを解説
『有害事象評価に関する判断基準』
日常の実務面で比較的頻度高く遭遇する代表的な事例を出来る限り列挙し提示
『グローバルPV体制構築とPVベンダーコントロール手法』
企業のpharmacovigilance部門の組織、稼働システムについて、最も的確なシステムとみなされている欧州のGVP moduleを紹介し、ポイントを解説
<< 書 籍 構 成 >>
<第1部:グローバルでの安全管理情報収集・報告編>
第1章:安全管理情報収集の目的について(はじめに)
第2章:安全管理情報の収集体制について
第3章:日米欧で目指す安全対策とは
<第2部:グローバルにおける日本との症例評価・有害事象評価の違いとコーディング>
第4章 有害事象における3要素のグローバルでの違い
第5章 有害事象/副作用の読み替え基準(ケーススタディ)、日英コーディング
第6章 海外症例(CIOMS)検討事例
<第3部:グローバルPV体制構築・ベンダーコントロールとPV Audit>
第7章:グローバルPVシステムとしてのEU GVP Moduleの理解
第8章:グローバルPV体制構築とPVベンダーコントロール手法
第9章:PVグローバル体制維持のためのPV Audit
日米欧3極の安全性情報管理の主な違い
| FDA (米国) | EMA (欧州) | PMDA (日本) | |
|---|---|---|---|
| 安全対策の主導 | FDA自らが主導・実施 | 企業側に主導・責任を託し、EMAが監視 | 基本は企業主導だが、ケースバイケースで厚労省が主導することもある |
| 治験時の姿勢 | 企業が提出したデータをFDAが最終評価 | 企業側に責任があり、EMAが評価する姿勢 | 企業側に責任があり、PMDAが評価する姿勢 |
| 市販後の情報収集 | 多くの情報を収集・保持し、高い精度の解析を実施 | 企業の「見える化」を強く要求 | EMA程強固な体制ではない |
| 当局報告要件 | 未知・重篤有害事象 | 未知・重篤副作用事象 | 未知・重篤副作用事象 |
※本書では上記のような3極の違いについて、具体的な症例例題を通して詳細に解説しています。
【各章のポイント】
第1部:『治験の安全管理情報』
治験時の安全管理情報について、さまざまな観点で取り扱いが日米欧で異なります。
<FDA>
基本的に企業が実施した治験時のデータをFDA側に提出させ、FDA側で安全性・有効性を最終的に評価決定する姿勢を取っています。
<EMA/PMDA>
治験を実施する企業側に責任が有するという考えに立脚し、それを規制当局が評価を行うという姿勢を取っています。
■未知重篤副作用の発現時
→規制当局への報告要否は?
※日米欧の規制当局が、治験時の関連性評価をどう考え、どう対応するのかの違い
※関連性評価に基づく記録の残し方
>例えば、適合性調査などで、「この関連性評価に至った根拠資料を提示して下さい。」などと査察官に言われることがあります。
<EMA/PMDA>
治験実施時には、治験責任医師等が関連性を否定する場合は、その根拠も合わせて取得するように依頼することが普通です。
<FDA>
この逆のケースが見受けられます。つまり、関連性があると評価した場合、何故関連性があると考えたのかの根拠もしくは論理的考察を求められることがあります。
第1部(2):『市販後の安全性情報』
幾つかの点で、日米欧での取り扱いの異なる点があります。
<FDA>
情報を収集する体制を万全にし、少しでも多くの情報を収集・保持することによって、より精度の高い解析を実施し、治験時と同様にFDA自らが安全対策を主導・実施する体制を整えています。
<EMA>
基本的に企業側に安全対策の主導・責任を託し、それをEMAが監視を行うという体制を取っています。したがって、企業の見える化を強く求めてきています。
<PMDA>
基本は企業主導で安全対策を実施する体制を取っていますが、EMA程強固な体制を整えている訳ではありません。時として日本当局である厚生労働省が主導して進めようとするものもあり、ケースバイケースで動いています。
第2部:『有害事象評価に関する判断基準』
安全性情報で扱う有害事象における「使用薬剤との因果関係」という場合の「因果関係」は、厳格にいうところの「因果関係」とピアソンの主張した「相関性」との間に位置するもの、あるいはそれらが相互に結合した観念であることが読み取れます。日常の実務面で比較的頻度高く遭遇する代表的な事例を出来る限り列挙し提示することによって基本的な考え方を解説します。
- [相当因果関係評価の基準]
- [関連性評価]
- [重篤性の基準]~日本と欧米の違い
- [予測性評価]
『有害事象/副作用の読み替え基準(ケーススタディ)』
腹痛・膵炎、アナフィラキシー反応、心筋梗塞、急性心不全、血圧低下、不整脈、高血糖
『日英コーディング』
皮疹、四肢浮腫、注射部位反応、腫瘍(新生物)、損傷、乱用(abuse)
第3部:『グローバルPV体制構築・ベンダーコントロールとPV Audit』
企業のPV部門の組織、稼働システムについて、最も的確なシステムとみなされている欧州のGVP moduleを紹介し、ベンダーコントロールを用いたグローバルPV体制構築について詳述。ベンダーを多用するPV体制維持には信頼性保証の手法が不可欠です。PV体制維持のためのPV Auditについて詳述します。
■EU GVP module I(Pharmacovigilance systems and their quality systems)とModule II(Pharmacovigilance system master file)、その根幹をなすのが、QMSのConceptおよびQualified Person for PV (QPPV)です。
- QPPVの権威(Authority)の比較
- QPPVの委託とPV Compliance
- QPPVの責務範囲
■グローバルPV体制構築とPVベンダーコントロール手法
- ESP選定のポイント
- ベンダーコントロールに必要な文書
- PV Agreement, SDEA, SLAの概念とその範囲
- 医学的評価へのESPの利用
<本書で取り上げている症例例題> ※日米欧での規制当局への報告の要否は??※
- 【例題1】
AB-12345という化合物の治験で、未知事象である間質性肺炎を発症し入院した症例があった。この事象に関し、治験責任医師は「間質性肺炎とAB-12345の関連性はある」との評価をしていた。一方、企業評価としては、「間質性肺炎とAB-12345の関連性はない」と評価を行った。
⇒ この場合、日米欧での規制当局への報告の要否はどうなると考えられるか? - 【例題-2】
被験者が治験参加前より、合併症である胃のポリープ切除術を入院下で実施する予定があった。(本治験は外来受診形態での治験)治験に参加し、最終投薬終了後、治験の追跡調査期間を残してはいたが、たまたまベッドの空きが出来た為、急遽胃のポリープ切除術を実施すべく入院した。
⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要はないのか? - 【例題-3】
患者が急性の腹痛に見舞われ、治験実施医療機関の外来を午後に受診したところ、点滴の処置が必要と判断され、その日の午後9時に点滴を開始し、午後11時に終了した。その後、帰宅するには遅い時間だったため、翌日の午前9時まで救急室のベッドで静養していた。医師コメントとしては、外来の救急室において処置は行ったが、その後帰りが遅くなっただけで、発生した事象に対する処置も通常外来時のものであるし、また入院にも至っていないので、重篤ではない。
⇒ これは、重篤症例として取り扱う必要はないのか?
※他にも合計25の実践的例題を収録!それぞれの例題に対する各国規制当局対応の違いを解説