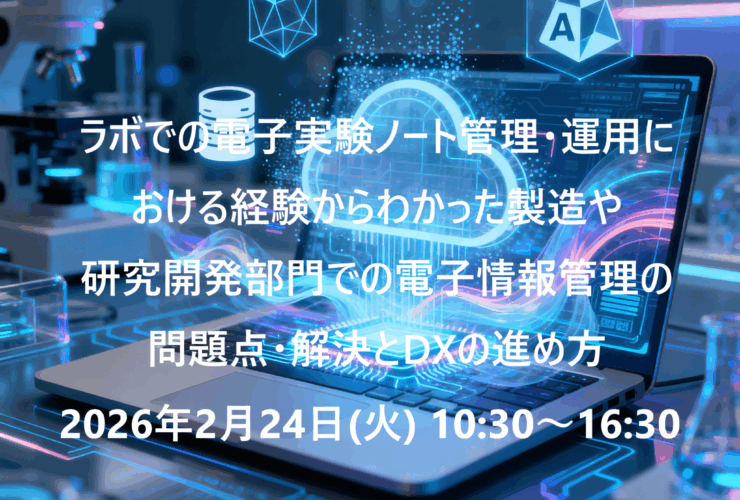GAA覇権戦争と AIデータセンター経済圏の衝撃への羅針盤
GAA覇権戦争と AIデータセンター経済圏の衝撃への羅針盤
― ハイパースケーラーの札束飛び交う仁義なき争い ―
激動の世界半導体業界を展望する、湯之上氏による【半導体関連企業の羅針盤シリーズ】
開催日
2025年12月16日(火) 13:00~16:30
2025年12月16日(火) 13:00~16:30
会場
東京・港区芝公園 コンベンションホール・AP浜松町 B1F Hルーム
東京・港区芝公園 コンベンションホール・AP浜松町 B1F Hルーム
受講形式
会場受講 / Live配信(アーカイブ付)
会場受講 / Live配信(アーカイブ付)
セミナー概要
生成AIが世界のルールを変えていく中、半導体覇権を決定づける GAA(Gate-All-Around)トランジスタにフォーカス。GAA技術開発力を始めとした各社攻防とその分析、巨大プラットフォーマーによる先端半導体の囲い込みとその影響、そして国家課題や地政学的視点をも含め、先端技術の枠を超えてGAAの本質に迫り、今後日本がとるべき戦略と勝ち筋を展望します。
注目のキーワード
講師紹介
湯之上 隆 氏
微細加工研究所 所長
専門分野
半導体技術(特に微細加工技術)、半導体産業論、経営学、イノベーション論
略歴
- 1987年3月 京都大学大学院工学研究科修士課程原子核工学専攻を卒業
- 1987年4月〜2002年10月 日立製作所・中央研究所、半導体事業部、デバイス開発センター、エルピーダメモリ(出向)、半導体先端テクノロジーズ(出向)にて、半導体の微細加工技術開発に従事(16年間)
- 2000年1月 京都大学より工学博士取得。学位論文「半導体素子の微細化の課題に関する研究開発」
- 2003年4月〜2009年3月 長岡技術科学大学・極限エネルギー密度工学研究センター客員教授
- 2003年10月〜2008年3月 同志社大学専任フェローとして、技術者の視点から半導体産業の社会科学研究に従事
- 2010年夏〜現在 微細加工研究所を設立、所長(主たる業務はコンサルタント、調査・研究、講演、原稿執筆)
主な著書
- 『日本半導体敗戦』(光文社、2009年)
- 『電機半導体大崩壊の教訓』(日本文芸社、2012年)
- 『日本型モノづくりの敗北』(文春新書、2013年)
- 『半導体有事』(文春新書、2023年)
連載記事
- メルマガ『内側から見た「半導体村」今まで書けなかった業界秘話』(隔週配信)
- EE Times Japan 『湯之上隆のナノフォーカス』(月1回)
- 日本ビジネスプレス『日本半導体・敗戦から復興へ』(月1回)
- ビジネスジャーナル『半導体こぼれ話』(月1回)
- 伊勢新聞『半導体漫遊記』(隔週)
電気学会フェロー。電気学会論文誌編修長、技術士試験委員、電気主任技術者試験委員などを歴任。2007年電気学会の自動車用パワーエレクトロニクス関係委員会の委員長を務めてきた。
得られる知識
GAAトランジスタの本質
GAAトランジスタとは何か、その技術的特徴と重要性を理解
主要メーカーの競争状況
TSMC・Samsung・Intel・Rapidusの2nm競争の現状と展望
EUV導入と競争力
EUV導入台数が競争力に与える影響の分析
AIデータセンターの拡大
AIデータセンターの爆発的拡大とGPU・HBM・DRAM・SSDの需要急増
AIインフラ危機
電力・水・土地の奪い合い(AIインフラ危機)の実態
投資戦略の理解
ハイパースケーラー(Microsoft、Google、Amazon、Meta、OpenAI)の投資戦略、前払い契約・長期囲い込みモデル
日本の戦略と勝ち筋
日本が取るべき戦略と勝ち筋の具体的指針
受講対象者
- 半導体関連企業(半導体メーカー、装置メーカーとその部品、材料、設備メーカー、半導体材料メーカー)の経営者、営業、マーケティング、技術者
- 半導体を搭載しているセットメーカー(クルマ、スマホ、PC、サーバー、クラウド、デジタル家電)の関係者
- 半導体産業の動向に関心のある政治家、経済産業省の官僚
- AIデータセンターやハイパースケーラーのビジネスに関わる方
プログラム
1. イントロダクション
- 1.1 自己紹介
- 1.2 本セミナーの概要と結論
2. 生成AIが変えた世界のルール
- 2.1 AIデータセンターが引き起こすパラダイム転換
- 2.2 AIデータセンターがGPU・HBM・メモリ・電力を食い尽くす
- 2.3 半導体は国家の命運を握る「戦略インフラ」へ
3. GAAトランジスタの新時代へ
- 3.1 GAA(Gate-All-Around)構造とプロセスフロー
- 3.2 GAAを巡る製造装置メーカーの攻防
- 3.3 GAA、BSPDN、High NA、CFET…次世代技術の分岐点
4. 先端半導体メーカーの戦略と現在地
- 4.1 TSMC(ファウンドリの王者)
- 4.1.1 EUV157台体制とN2量産への道
- 4.1.2 N2に殺到するファブレスとCoWoSのキャパシティ
- 4.1.3 N2、A16、A14、A10へのロードマップと技術戦略
- 4.2 Samsung(ファウンドリもメモリも大苦戦)
- 4.2.1 N3でGAAを導入するも歩留り上がらず
- 4.2.2 N2で米Teslaと大型契約(生き延びた)
- 4.2.3 HBMとDRAMでSK hynixに劣後し苦境に陥る
- 4.3 Intel(かつての半導体王者の凋落)
- 4.3.1 「4年で5 Node」が失敗し窮地に陥ったIntel
- 4.3.2 「トップ10からの脱落」「AI半導体は手遅れ」「リストラはマラソン」
- 4.3.3 社運を賭ける「A14」に顧客がつかなかったら最先端から撤退
- 4.3.4 Intelの将来は「ファブレス」「身売り」「国営」か?
- 4.4 Rapidus(N2への無謀な挑戦)
- 4.4.1 NHKスペシャル(9月7日)の紹介
- 4.4.2 当てにしていたテンストレントもTSMCに先を越された
- 4.4.3 500億円でEUVを買う?
- 4.4.4 破綻しているRapidusのビジネスモデル
5. ハイパースケーラーが仕掛ける資源争奪戦
- 5.1 NVIDIAを中心に形成されるAIサプライチェーン
- 5.2 OpenAI・Microsoft・Googleの前払い契約モデル
- 5.3 「札束でウェハを奪い合う時代」へ
- 5.4 台湾・韓国・米国・日本の争点
6. AIデータセンターがもたらす地政学的インパクト
- 6.1 電力・水・土地:半導体を超える国家課題
- 6.2 「1拠点」=「原発1基」の時代が到来
- 6.3 チップ戦争から「電力戦争」への移行
7. 結論とメッセージ
- 7.1 GAAはトランジスタ技術ではなく「国家戦略技術」
- 7.2 AIデータセンター経済圏が覇権を決する
- 7.3 日本はどこで戦い、どのように勝つべきか
□質疑応答・名刺交換(会場受講限定)□
※より深刻・重大な内容に講演内容を変更する可能性がございますので、予めご了承ください。